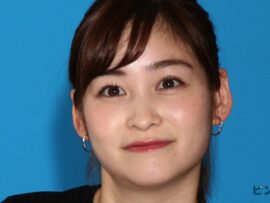大阪・関西万博の玄関口、大阪メトロ中央線「夢洲駅」が開業しました。1970年の大阪万博でも新たな鉄道と駅が誕生し、街の発展に大きく貢献しました。今回は、日本初の大規模ニュータウン「千里ニュータウン」と北大阪急行電鉄の誕生秘話、そして大阪万博との関係性について掘り下げてみましょう。
戦後の労働力不足と金の卵
第二次世界大戦後、日本は驚異的な経済復興を遂げました。しかし、その一方で都市部では深刻な労働力不足が発生しました。町工場や個人商店は人材確保に奔走し、地方の農村部では家業を継げない次男三男が職を求めて都会へと流れていきました。
彼らは「金の卵」と呼ばれ、貴重な労働力として歓迎されました。しかし、その実態は過酷な労働環境でした。住み込みで長時間働き、家事や育児も強いられることも珍しくありませんでした。結婚し、家庭を持つようになると、彼らにとって住宅の確保が大きな課題となりました。
 1970年の大阪万博会場地跡地に残る太陽の塔
1970年の大阪万博会場地跡地に残る太陽の塔
ニュータウン建設の波と千里ニュータウンの誕生
金の卵たちの住宅需要に応えるため、大都市近郊では大規模ニュータウンの建設計画が次々と立ち上がりました。その先駆けとなったのが、1958年に大阪府が計画を策定した「千里ニュータウン」です。
都市計画の専門家、山田太郎氏(仮名)は、「千里ニュータウンは、当時の日本の住宅事情を大きく変えた画期的なプロジェクトでした。計画的な街づくり、緑豊かな環境、そして交通インフラの整備など、多くの都市計画に影響を与えました」と語っています。
大阪万博と北大阪急行電鉄
千里ニュータウンへのアクセス向上を目的として、北大阪急行電鉄が建設されました。1970年の大阪万博開催に合わせて、江坂-万国博中央口間が開業し、多くの来場者を輸送しました。
鉄道ジャーナリストの佐藤弘子氏(仮名)は、「北大阪急行電鉄の開業は、千里ニュータウンの発展に大きく貢献しました。交通の便が向上したことで、人口増加が進み、活気あふれる街へと成長しました」と述べています。
まとめ
夢洲駅の開業は、1970年の大阪万博を彷彿とさせます。当時の万博開催が千里ニュータウンや北大阪急行電鉄の誕生を促したように、今回の万博もまた、大阪の街に新たな変化をもたらすでしょう。夢洲駅を起点に、大阪・関西万博、そしてその先の未来へ、期待が高まります。