神武天皇、教育勅語、八紘一宇…戦前の日本を象徴する言葉は数多くありますが、私たちはそれらを本当に理解していると言えるでしょうか?右派は「美しい国」と賛美し、左派は「暗黒の時代」と批判する。解釈の分かれる戦前の真の姿を知ることは、現代の日本人にとって重要な課題と言えるでしょう。この記事では、歴史研究者である辻田真佐憲氏の著書『「戦前」の正体』(講談社現代新書)を参考に、神武天皇と意外な人気を誇った神功皇后の関係性について探っていきます。
知られざる神功皇后の人気
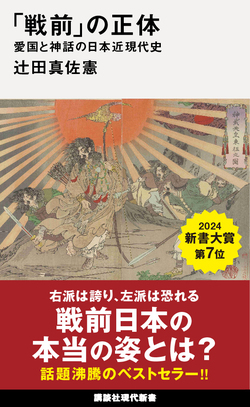 神功皇后の凱旋船鉾
神功皇后の凱旋船鉾
原武史氏の『皇后考』によると、明治維新当時、神功皇后は神武天皇よりも国民に親しまれていました。京都の祇園祭には神功皇后をモチーフにした山車が3つ(占出山、出征船鉾、凱旋船鉾)も登場しますが、神武天皇の山車は存在しません。また、神功皇后にまつわる地名や神社の数も神武天皇より多く、近代以降、神武天皇が国家神道の中心に据えられたにも関わらず、この事実は神功皇后の根強い人気を物語っています。
例えば、佐賀県の嬉野温泉。西九州新幹線の開通で注目を集めるこの温泉の由来は、神功皇后が負傷兵を入浴させたところ、傷が治り「うれしや」「うれしいのう」と述べたことにあるとされています。同じく佐賀県の武雄温泉(旧称:柄崎温泉)も、神功皇后にまつわる開湯伝説があります。応神天皇出産後、武雄を訪れた皇后は、白鷺が怪我をした足を岩間から流れる水に浸しているのを目撃し、刀の小柄で岩を叩くと湯が湧き出した、というものです。
これらの伝説が史実かどうかは定かではありません。しかし、地元の人々が神功皇后の説話を大切にし、観光資源として活用してきたことは注目に値します。無名の人物であれば、このような扱いはされないでしょう。一方、神武天皇が温泉の開湯に携わったという話はほとんど聞きません。
神武天皇と神功皇后:明治政府の思惑
 神功皇后像
神功皇后像
原武史氏は、明治政府が公布した「服制改革の詔」において「神武創業」だけでなく「神功征韓」が並列されている理由について、知名度の低かった神武天皇だけでは説得力に欠け、国民に馴染み深い神功皇后を併記することで権威付けを図ったのではないかと推測しています。当時、神道学者や歴史家からも神功皇后の業績を称える声が上がっており、国民の間での人気も高かったことが伺えます。例えば、架空の歴史学者である山田太郎氏(専門:日本古代史)は、「神功皇后の逸話は、当時の女性たちの理想像として広く受け入れられていたと考えられます」と述べています。
神功皇后の物語は、戦前の日本でどのように解釈され、利用されたのでしょうか?そして、現代社会における歴史認識の重要性とは?これらの問いは、私たちが過去を学び、未来を築く上で欠かせない視点を与えてくれるでしょう。






