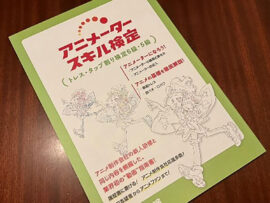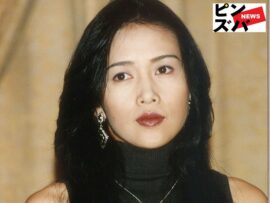中国経済の減速が深刻化する中、北京では生活困窮者を支援する「思いやり食堂」と呼ばれる飲食店が増えています。無料、あるいは格安で食事を提供するこれらの店は、厳しい現実の中で人々の温かい支えとなっています。しかし、その背景には雇用不安や社会保障制度の問題など、中国社会が抱える深刻な課題が潜んでいます。
経済の減速が生む「思いやり食堂」の増加
北京市郊外の中華料理店「小湘旺・宋庄店」では、「職がなく、生活が苦しければ、お代は結構です」という看板を掲げ、困窮者に無料で食事を提供しています。メニューにない「39元(約850円)の唐辛子肉炒め丼」を注文することで、お金に困っている人でもプライドを傷つけずに食事ができるという配慮もされています。
 alt
alt
店長の卜勝男さんは、路上清掃員の困窮した生活を目の当たりにしたことがきっかけでこの取り組みを始めたといいます。「誰もが大きなストレスにさらされている今の世の中、少しでも手助けをしたい」と語る卜さんの思いやりは、多くの困窮者の支えとなっています。
他にも、配達員向けに格安の食べ放題ランチを提供する「洞庭家宴・広渠門店」など、様々な形で支援を行う飲食店が増えています。これらの「思いやり食堂」は、厳しい経済状況下で人々の支え合いを象徴する存在となっています。
若者の雇用不安、社会保障制度の課題
しかし、「思いやり食堂」の増加は、中国経済の減速と雇用不安の深刻化を反映しているとも言えます。若年層の失業率は高止まりしており、安定した仕事に就けない働き手が多く存在します。
配達員やライドシェア運転手など、いわゆる「フレキシブルワーカー」は2億人を超え、就労人口の約3割を占めています。一見柔軟な働き方に見えますが、多くは非正規雇用であり、社会保障制度の恩恵を受けられないケースも少なくありません。

年金や医療保険の未加入も社会問題化しており、将来への不安を抱える若者が増えています。中国の社会保障制度は少子高齢化や地方財政の逼迫により、既に財源が悪化しています。保険料未納の増加は、この制度の土台を揺るがしかねない深刻な問題です。
中国社会の未来への課題と政府の対応
中国・対外経済貿易大学の西村友作教授は、「今後は中低所得層の収入が落ち込むことで、貧富の格差が広がる可能性がある」と指摘しています。多くの国民が将来への不安を抱えている状況では、消費の低迷が続き、経済再建は困難になります。
中国政府は低所得者の新たな認定基準を定め、生活困窮世帯への支援強化に乗り出しました。しかし、社会保障制度の抜本的な改革や雇用対策など、より根本的な解決策が必要とされています。
3月上旬に開催される全国人民代表大会(全人代)では、習近平指導部がどのような政策を打ち出すのか、世界中の注目が集まっています。中国社会の未来にとって、弱者を支えるセーフティーネットの構築と、国民の安心感の回復が重要な課題となるでしょう。