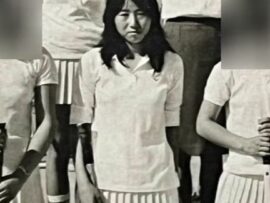近年の世界情勢の中で、中国経済への依存度を低減する「脱中国依存」の動きが加速しています。米中摩擦、コロナ禍、ウクライナ紛争など、世界経済の分断が進む中で、各国はサプライチェーンの見直しを迫られています。 日本も例外ではなく、中国の経済的威圧に対する懸念が高まっている今、どのように「脱中国依存」を進めていくべきなのでしょうか。
経済的威圧の実態と日本の課題
中国は世界経済での存在感を強める一方で、その力を利用した「経済的威圧」をたびたび行っています。国際法上明確な定義はありませんが、貿易制裁や輸出制限など、自国の利益のために他国に圧力をかける行為が問題視されています。
過去の事例と現状
過去には、尖閣諸島の問題をきっかけに、レアメタルの輸出制限が行われました。そして現在、レアメタルやレアアース、さらには福島第一原発の処理水を巡る日本産海産物の輸入停止措置など、中国による経済的威圧は再び顕在化しています。
 レアメタルの鉱石
レアメタルの鉱石
日本は中国への経済的依存度が高く、「脱中国依存」は容易ではありません。第一生命経済研究所の主席エコノミスト、西濱徹氏(仮名)は著書『インドは中国を超えるのか』(ワニブックス刊)の中で、日本の中国依存の現状と課題を分析しています。西濱氏は、「中国との経済関係を完全に断ち切ることは非現実的だが、特定の分野への過度な依存はリスクとなる。多角化を進め、サプライチェーンの強靭性を高める必要がある」と指摘しています。(出典:『インドは中国を超えるのか』ワニブックス)
「脱中国依存」への道筋
では、日本はどのように「脱中国依存」を実現していくべきなのでしょうか。いくつかの重要なポイントを見ていきましょう。
サプライチェーンの多角化
特定の国への依存を避けるため、生産拠点や調達先を分散させることが重要です。ASEAN諸国やインドなど、中国以外の国との経済連携を強化していく必要があります。
国内生産の強化
国内での生産能力を高めることで、海外からの輸入への依存度を減らすことができます。技術開発や人材育成への投資が不可欠です。
国際協調の重要性
「脱中国依存」は日本だけで解決できる問題ではありません。国際社会と連携し、共通のルール作りや情報共有を進めることが重要です。
日本にとって「脱中国依存」は、経済安全保障の観点からも喫緊の課題です。困難な道のりではありますが、持続可能な経済成長を実現するためには、戦略的な取り組みが不可欠です。
未来への展望
中国との経済関係をゼロにすることは現実的ではありません。しかし、リスクを最小限に抑えながら、バランスのとれた関係を構築していく必要があります。多角的な視点と柔軟な対応が求められるでしょう。