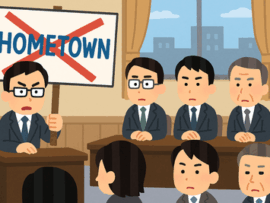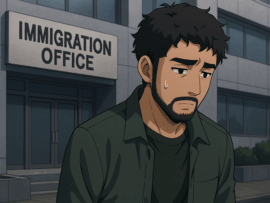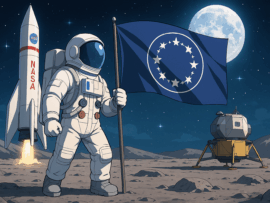近年、小学生の間でもメイクへの関心が高まり、SNSや動画を参考に高度なメイクに挑戦する子が増えています。一方で、子どもを持つ親、特に父親は、この「低年齢化」をどのように捉えているのでしょうか?本記事では、父親の視点から子どもたちのメイク事情を探り、親子関係への影響について考察します。
メイクを通じた親子の会話:意外な発見と新たな繋がり
出版社勤務のKさんは、中学1年生の娘さんが小学5年生頃からメイクに興味を持ち始めたと話します。きっかけは、クラスに転校してきた大人っぽい女の子の影響だったそうです。Kさんは、娘さんがお小遣いで韓国コスメを購入する姿を見て、YouTubeの影響力の大きさを実感したと言います。
「娘に韓国コスメの良さを教えてもらった時は、その知識の深さに驚きました」とKさん。このエピソードは、メイクが親子の新たなコミュニケーションツールとなり得ることを示唆しています。思春期を迎えるにつれ、親子の会話が減っていく傾向にありますが、メイクという共通の話題を通じて、子どもたちは普段とは違う一面を見せてくれるかもしれません。
 alt
alt
小学4年生と幼稚園生の娘を持つTさんも、子どもたちのメイクへの関心の高さに驚いたと言います。「男性もメイクをする時代。そういう時代なのだと見守っています」とTさんは語ります。
親としての心配と適切な指導のバランス
子どもたちのメイクへの関心を肯定的に捉えつつも、親として心配な面もあるのは当然です。「お祭りに友達と出かける時の濃いメイクは心配」とKさんは言います。過度なメイクによって、子どもたちが危険な目に遭わないか、保護者としては不安になるのも無理はありません。
美容専門家の佐藤さんは、「子どものメイクは、肌への負担を最小限にすることが重要です。低刺激性の化粧品を選び、クレンジングをきちんと行うように指導しましょう」とアドバイスしています。また、「メイクを通じて自己表現を学ぶことは大切ですが、年齢に合わせた適切なメイクを心がけるように親子で話し合うことが重要です」とも述べています。
健全なメイク習慣を育むために
子どものメイクに対する父親の視点は様々ですが、共通しているのは、子どもたちの成長を見守りながら、適切な指導を行いたいという思いです。メイクを通じたコミュニケーションを大切にしつつ、健全なメイク習慣を身につけるようにサポートしていくことが重要と言えるでしょう。