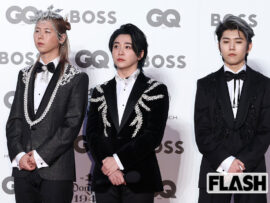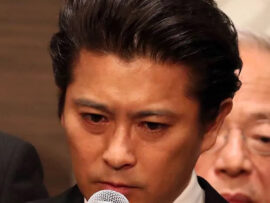八潮市の道路陥没事故、記憶に新しいのではないでしょうか。この事故は、老朽化した下水道管が引き起こしたもので、実は全国的な問題となっています。今回は、日本の下水道管の現状と、私たちが安心して暮らせる街づくりのために必要な対策について考えてみましょう。
老朽化が進む日本の下水道管の現状
現在、日本全国には約49万キロもの下水道管が張り巡らされています。しかし、そのうち標準耐用年数(50年)を超えた管路は、2022年時点で約3万キロにも及んでいます。このまま放置すれば、2032年には約9万キロ、2042年には約20万キロに達すると予測されており、まさに時限爆弾を抱えているような状況です。国土交通省は各自治体に対し点検を要請していますが、本当にそれで十分なのでしょうか?
 alt_text埼玉県八潮市の道路陥没事故現場。老朽化した下水道管が原因とみられる。(写真:共同通信社)
alt_text埼玉県八潮市の道路陥没事故現場。老朽化した下水道管が原因とみられる。(写真:共同通信社)
神戸大学大学院工学研究科の小池淳司教授は、「国は地方に管理・点検を求めるのではなく、国が主体的になって点検するべきだ」と指摘しています。その背景には、地方分権とインフラ投資の相性の悪さがあるようです。
地方分権の落とし穴:インフラ投資の後回し
地方分権は、地域の実情に合わせた政策展開を可能にするというメリットがある一方で、インフラ投資のような巨額の費用が必要な事業は後回しになりがちです。「教育や福祉を優先し、インフラへの投資は抑制する」という判断をする自治体が出てくる可能性も否定できません。結果として、地域によってインフラの安全性に格差が生じる恐れがあります。
国民の生命・財産を守るインフラ整備は、国の責任です。財政難や人材不足に悩む自治体にすべてを任せきりにするのではなく、国が主導権を握り、必要な予算と人材を確保していく必要があるのではないでしょうか。

国主導の対策で安全・安心な街づくりを
八潮市の事故は、私たちにインフラ老朽化の深刻さを改めて突きつけました。このような事故を未然に防ぐためには、国が中心となって下水道事業を管理し、計画的な更新投資を進めていく必要があります。 専門家の中には、民間企業のノウハウを活用した効率的な維持管理体制の構築を提言する声もあります。
まとめ:未来への投資で安全な社会基盤を築く
下水道管の老朽化問題は、私たちの生活の安全基盤を脅かす重大な課題です。国、地方自治体、そして私たち国民一人ひとりが危機感を共有し、未来への投資としてインフラ整備に取り組むことが、安全・安心な社会の実現につながるのではないでしょうか。