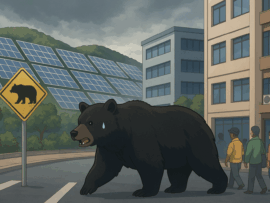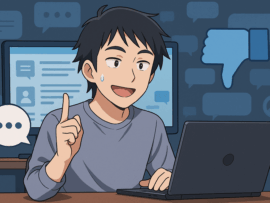硫黄島の戦いは、80年以上前の1945年2月19日に始まりました。この激戦地で多くの日本兵が命を落とし、そのうち1万人は今もなお行方不明のままです。なぜこれほど多くの兵士が行方不明なのでしょうか?硫黄島では一体何が起こっていたのでしょうか?民間人の上陸が原則禁止されているこの島に4度上陸し、日米の機密文書を徹底調査したノンフィクション『硫黄島上陸 友軍ハ地下ニ在リ』を元に、硫黄島の知られざる真実を紐解いていきます。
核兵器と硫黄島:戦略拠点の変遷
 硫黄島の地下壕
硫黄島の地下壕
名古屋外国語大学の真崎翔氏は、核戦略における硫黄島の重要性が過去と大きく変化したと指摘しています。冷戦時代、硫黄島は核兵器の秘密貯蔵場所としての役割を担っていましたが、原子力潜水艦の登場により、その重要性は低下しました。現代の核戦略において、硫黄島に核兵器を置くメリットはほとんどないと言えるでしょう。秘密の核貯蔵基地としての役割は、もはや過去のものとなっています。
では、核戦略上の要衝ではなくなった硫黄島になぜ民間人の上陸が禁止されているのでしょうか?真崎氏は、自衛隊のレーダー基地の存在が理由の一つではないかと推測しています。硫黄島は古くから電波通信の軍事施設の拠点であり、中国の軍事活動の活発化に伴い、その重要性はさらに高まっています。繊細なレーダー基地を守るため、民間人の上陸を制限していると考えられます。
遺骨収集と滑走路:放置されたままの悲願
 硫黄島の戦闘跡
硫黄島の戦闘跡
遺族の長年の悲願である、米軍と自衛隊が共同使用している滑走路の発掘調査は、一向に実現していません。真崎氏は、米国側は戦没者への敬意を払っており、遺骨収集のための滑走路撤去要請には応じる可能性が高いと見ています。しかし、日本側が「触らぬ神に祟りなし」の精神で、米国への積極的なアプローチを避けているのではないかと指摘しています。
日本政府が米国に要請すれば、代替地の提供を求められる可能性が高く、莫大な労力と費用が必要となります。そのため、遺骨収集は「時間と共に解決する問題」と捉え、現状維持を続けているのではないでしょうか。軍事評論家の田中氏は、「日本政府は、遺族の気持ちよりも日米関係を優先しているように見える。これは国家としての責任放棄と言えるだろう」と批判しています。
硫黄島のイメージ:国民の無関心と国の不作為
多くのメディアが硫黄島を「地獄のような島」として報道してきたため、国民の間には硫黄島に対する誤ったイメージが定着しています。国はこのイメージを利用し、「人が住めない島に島民を帰還させる必要はない」という論理で、日米の基地化を正当化してきた側面があります。国民の無関心も相まって、硫黄島の現状は放置されたままとなっています。
歴史研究家の佐藤氏は、「硫黄島の真実を伝えるためには、国民一人ひとりが関心を持つことが重要だ。メディアも、硫黄島の歴史や現状をより深く掘り下げて報道する必要がある」と訴えています。
硫黄島の戦いは、今もなお多くの謎に包まれています。1万人の行方不明兵士の遺骨収集は、国家としての責務です。国民の関心を高め、政府に行動を促すことが必要不可欠です。