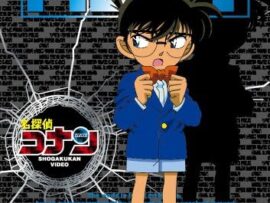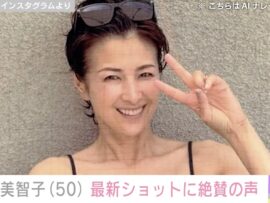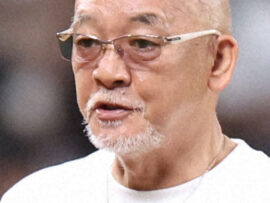給食費無償化は、多くの家庭にとって朗報であり、教育の平等化に貢献する重要な政策です。しかし、その裏側では、物価高騰やコロナ禍の影響など、様々な課題も浮き彫りになっています。この記事では、無償化のメリット・デメリット、そして未来の食育について考えていきます。
物価高騰という壁:現場の苦悩と献立への影響
給食費無償化は、家計の負担軽減に大きく貢献しています。しかし、急激な物価高騰は、学校給食の現場に大きな影を落としています。東京都文京区で学校栄養士として働く松丸奨氏(仮名)は、「物価高の影響で給食の質を維持するのが非常に困難になっている」と語ります。
予算の制約の中で、食材費の削減は避けられない状況です。おかずの品数を減らす、肉の量を減らす、魚の種類を変えるなど、様々な工夫が凝らされています。しかし、これらの工夫は、子どもたちの食体験にも影響を及ぼしています。例えば、ブランド米からブレンド米に変更したことで、「ご飯の匂いが気になる」という声が上がり、残食が増えてしまった学校もあるそうです。
 alt
alt
また、油の使い回し回数が増えている学校も少なくありません。酸化度は基準値内とはいえ、風味や栄養価への影響は懸念されます。松丸氏は、「おいしい給食を提供することが難しくなっている」と現状を危惧しています。
コロナ禍の影響:簡易給食の定着と食育への懸念
コロナ禍で導入された簡易給食も、給食の質低下の一因となっています。感染対策のため、配膳は担任の先生が行うようになり、品数や食材の種類が削減されました。この簡易給食が、コスト削減を目的として定着しつつある現状に、松丸氏は警鐘を鳴らします。「サラダやデザートが削られ、栄養バランスが崩れている学校もある。子どもたちの食育への影響が心配だ」と語ります。
給食は、子どもたちにとって食の大切さを学ぶ貴重な機会です。多様な食材に触れ、バランスの良い食事を体験することで、健全な食習慣を身につけることができます。しかし、現在の状況では、食育の機会が損なわれるリスクが高まっていると言えるでしょう。
無償化の未来:持続可能な制度設計と質の確保に向けて
給食費無償化は、多くのメリットをもたらす一方で、解決すべき課題も山積しています。自治体間の予算格差もその一つです。松丸氏は、「各自治体に丸投げするのではなく、国が主導して給食の質を一定水準に保つべきだ」と提言します。

持続可能な給食費無償化制度を実現するためには、予算の確保だけでなく、調理現場の負担軽減も重要な課題です。人手不足や長時間労働など、調理員の労働環境の改善も喫緊の課題です。
子どもたちの未来を支える給食。無償化の恩恵を最大限に活かし、食育の充実を図るためには、関係者全員が協力し、より良い制度を構築していく必要があるでしょう。