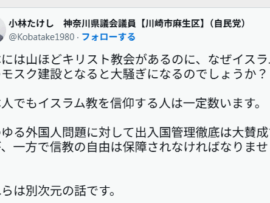JA(農業協同組合)は本来、組合員である農家の利益を守る組織であるはずです。しかし、近年、共済(保険)事業における不正販売が問題視されています。今回は、元日本農業新聞記者の徹底取材に基づき、JA共済の「むてきプラス」という商品をめぐる問題点、特に顧客に不利益な契約変更の勧誘の実態について深く掘り下げていきます。
「むてきプラス」とは?そして、なぜ問題なのか?
「むてきプラス」は、JA共済が提供する建物更生共済の一つで、火災、台風、地震などの災害による損害を保障するだけでなく、災害によるケガや死亡に対する共済金も支払われる商品です。以前販売されていた「むてき」の改訂版として登場しましたが、この「むてきプラス」への切り替え勧誘が、顧客にとって不利益となるケースが多いと指摘されています。
 JA共済の建物更生共済「むてきプラス」に関する説明
JA共済の建物更生共済「むてきプラス」に関する説明
JAとぴあ浜松の事例では、ライフアドバイザー(LA)が「むてき」から「むてきプラス」への切り替えを積極的に勧誘し、「むてきプラス」の加入割合が急増しました。しかし、この切り替えが多くの顧客にとって損失につながっているというのです。
予定利率の低下:切り替えで損をするカラクリ
LAが切り替えを勧める主なターゲットは、「むてき」で高額な保障額と積立金を持ち、解約返戻金が多い顧客です。例えば、評価額3000万円の住宅に対して、同額の保障額と数百万円の積立金を設定し、長期間加入している顧客などが該当します。
LAはこれらの顧客に対し、「むてき」と同じ保障額3000万円で「むてきプラス」への切り替えを提案します。しかし、共済商品の掛け金は予定利率(期待利回り)に基づいて決定されるため、以前と比べて予定利率が大幅に低下している現在、保障額を同じにして切り替えることは、単純に損をする行為なのです。
金融庁が発表する標準利率は、1990年代前半は5%台でしたが、現在は0%台まで低下しています。JA共済の予定利率も同様に、1990年代の8%台から2021年末時点では0.5〜0.8%まで低下しています。
共済専門家の山田一郎氏(仮名)は、「予定利率の低下を理解せずに、以前と同じ保障額で新しい商品に切り替えることは、将来受け取れる金額が減るリスクを高める可能性があります」と警鐘を鳴らしています。
顧客にとって本当に有利な提案とは?
顧客にとって本当に必要なのは、現状の保障内容や将来のライフプランを考慮した上で、最適な保障額や積立金を見直すことです。LAは、顧客の利益を最優先に考え、適切なアドバイスを提供する必要があります。
まとめ:消費者は賢く選択を
JA共済の「むてきプラス」への切り替え勧誘に見られるように、金融商品には複雑な仕組みやリスクが潜んでいます。消費者は、提供される情報に惑わされることなく、自身の状況をしっかりと理解し、賢く選択することが重要です。
この問題について、JA共済中央会に取材を申し込んだものの、回答は得られませんでした。今後のJA共済の対応に注目が集まります。