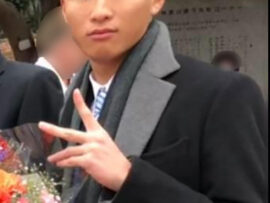JA(農業協同組合)は、組合員である農家の利益を守る組織であるはずなのに、なぜ「不正販売」や「自爆営業」が横行しているのでしょうか?本記事では、元日本農業新聞記者の著者による徹底取材に基づき、共済(保険)事業と信用(銀行)事業への依存、そして職員に課せられた過大なノルマがもたらす「不都合な真実」に迫ります。JAは本当に農家の味方なのか?全国に広がる巨大組織の腐敗の実態を紐解いていきます。
過大なノルマと不正販売の蔓延
JAとぴあ浜松で発覚した不正販売は、氷山の一角に過ぎません。金融事業に依存している多くのJAで、同様の問題が起きている可能性が高いのです。その背景にあるのは、職員に課せられた過大なノルマと、ノルマ達成度によって大きく変動する手当です。
 JA職員のノルマ達成度による年収格差
JA職員のノルマ達成度による年収格差
JAとぴあ浜松の職員Aさんは、以下のように語っています。
「私たちの農協には1300人の職員がいますが、そのうちノルマが課せられるのはライフアドバイザー(LA)職員、複合渉外職員、各課の主任と係長を合わせて約300人です。しかも、私たちの農協のノルマは全国でもトップクラスの額です。民間の保険会社社員と話す機会も多いのですが、『農協はノルマが多い』とよく言われます。しかも、その額は年々増加しています。ノルマを達成すればボーナスが増え、達成できなければ減らされるため、皆、必死になっているのです。」
ノルマ達成のための顧客軽視
ノルマ達成のため、顧客に不利な商品への切り替えを勧めるケースも少なくありません。これは、過去に問題となった「かんぽ生命の不正販売」と同様の構図です。顧客の利益よりも、自身のノルマ達成、ひいては農協の利益を優先する風潮が蔓延しているのです。
顧客の信頼を裏切る行為
JAは地域に根ざした組織であり、組合員からの信頼も厚いはずです。しかし、過大なノルマによって、その信頼を裏切る行為が行われているとしたら、大きな問題です。農家にとってJAは重要なパートナーであり、その信頼関係が損なわれることは、農業の未来にも悪影響を及ぼしかねません。
専門家の見解
農業経済の専門家であるB教授(仮名)は、次のように指摘しています。「JAは本来、農家の生活を守るための組織です。しかし、金融事業への依存度が高まり、ノルマ至上主義に陥っている現状は、本来の目的から逸脱していると言わざるを得ません。JAは、組合員の声に真摯に耳を傾け、信頼回復に努める必要があるでしょう。」
JA改革への道
JAが本来の役割を取り戻すためには、ノルマの見直しや、職員への適切な教育、そして透明性の高い経営体制の確立が不可欠です。農家とJAが真のパートナーシップを築けるよう、改革が求められています。