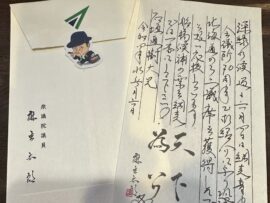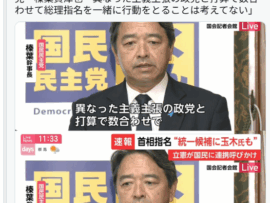JA(農業協同組合)は、組合員である農家の生活を支える組織として設立されました。しかし、近年では「不正販売」や「自爆営業」といった問題が蔓延し、本来の理念から乖離しているとの指摘も少なくありません。元日本農業新聞記者の徹底取材に基づいた書籍『農協の闇』では、共済(保険)事業と信用(銀行)事業への過度な依存、そして職員に課せられた過大なノルマが生み出す「不都合な真実」が赤裸々に描かれています。今回は、この書籍から一部を抜粋・再編集し、JA職員の苦悩と不正の実態に迫ります。
過大なノルマと自爆営業の悪循環
JA職員にとって、共済商品の販売ノルマは大きなプレッシャーとなっています。ノルマ達成のために、職員自ら不要な共済に加入したり、家族や親戚、友人知人に懇願して加入を依頼する「自爆営業」は、もはや業界の常識と化しているとも言われています。
 JA職員のノルマ達成圧力
JA職員のノルマ達成圧力
本人の同意なき加入:横行する不正行為
自爆営業のさらに深刻な問題は、本人の了解を得ずに共済商品に加入させるケースが横行している点です。職員はノルマ達成のため、友人や知人の家族、特に遠方に住む子供など、直接連絡を取りづらい相手をターゲットにすることがあります。親にだけ了解を取り、子供には無断で加入手続きを進めるという悪質な手口も存在します。
ずさんな加入審査の実態
このような不正行為は、どのようにして可能になっているのでしょうか?本来、共済への加入には本人確認書類と本人の署名が必要ですが、タブレット端末による電子署名の導入により、筆跡の確認が難しくなり、親が子供の代わりに署名しても発覚しにくくなっているのが現状です。本人確認書類も、親が子供の健康保険証を無断で使用するケースが少なくありません。
職員による通帳の不正作成
さらに、職員が支払いを肩代わりする人の通帳を勝手に作成し、それを所持するという深刻な問題も発生しています。両親の同意と本人確認書類さえあれば、口座開設の申込書を代筆し、印鑑も職員が用意することで、本人に知られることなく通帳が作成されてしまいます。職員はなぜこのような不正行為に手を染めてしまうのでしょうか?それは、過大なノルマのプレッシャーと、組織ぐるみで不正を黙認する風潮が背景にあると考えられます。
専門家の見解:JA改革の必要性
農業経済学者である山田太郎氏(仮名)は、JAにおけるノルマ主義の問題点を指摘し、「組合員のためではなく、自己保身に走る組織風土を改革しなければ、JAの信頼は失墜する一方だ」と警鐘を鳴らしています。
JAの未来:信頼回復への道
JAは、日本の農業を支える重要な役割を担っています。しかし、不正販売や自爆営業といった問題を放置すれば、組合員からの信頼を失い、組織の存続さえ危ぶまれる事態になりかねません。JAは、本来の理念に立ち返り、組合員の声に耳を傾け、透明性の高い組織運営を行う必要があります。
まとめ:JA改革への期待
JAにおける不正問題の根底には、過大なノルマと、それを黙認する組織風土が存在します。JAは、これらの問題に真摯に向き合い、改革を進めることで、組合員からの信頼を回復し、日本の農業の発展に貢献していくことが求められています。