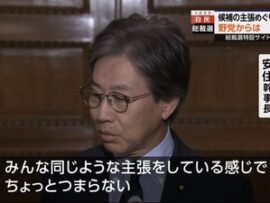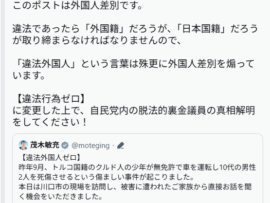春爛漫の季節、桜が満開に咲き誇る中、我が家の双子の娘たちがそれぞれ卒業式を迎えました。医療的ケアが必要な長女は12年間通った特別支援学校を、次女は15年間通った一貫校を巣立ち、新たな人生の門出を迎えました。今回は、双子の娘たちの卒業と、インクルーシブ教育への想いを綴りたいと思います。
特別支援学校と一貫校:それぞれの学び舎での成長
 alt:満開の桜並木の写真。卒業式シーズンを象徴するような美しい風景。
alt:満開の桜並木の写真。卒業式シーズンを象徴するような美しい風景。
双子の娘と、年子の息子。3人はまるで三つ子の様に、いつも一緒に過ごしました。食事の時間も、トイレに行くタイミングさえも同じだった幼い頃。そんな3人が、それぞれの道を歩み始めたのは、長女が児童発達支援センターへ、次女が一貫校の付属幼稚園へ通い始めた時でした。
当時、私は長女の障害を受け入れることはできていましたが、”双子”という事実にこだわり続けていました。「もし長女が健常児だったら、一緒に幼稚園に通えたのに…」という思いが頭をよぎる日々。さらに、人見知り、場所見知りが始まった長女は、先生や教室を見る度に泣きじゃくり、その姿を見る度に胸が締め付けられました。「こんな思いをさせてまで、通園させる必要があるのだろうか?」と自問自答することもありました。
それぞれの場所で輝く娘たち
しかし、親子共にそれぞれの環境に慣れていくにつれ、先生方の温かさ、熱心さに触れ、新たな発見がありました。個別支援を通して、長女は笑顔が増え、できることも増えていきました。おとなしかった次女は、歌が大好きになり、集団生活の中で自分らしさを発揮するようになりました。それぞれの学び舎で、娘たちは輝きを増していったのです。
インクルーシブ教育の重要性と日本の課題
長女が特別支援学校で12年間、愛情あふれる指導を受けて大きく成長した姿を目の当たりにし、改めてインクルーシブ教育の重要性を感じています。「インクルーシブ」「インクルージョン」とは、障害や多様性を排除するのではなく、共生していくことを意味します。
ハワイでの滞在経験を通して、インクルーシブ教育の先進的な取り組みを目の当たりにした私は、日本におけるインクルーシブ教育の現状に課題を感じています。例えば、文部科学省の調査(※架空の調査)によると、インクルーシブ教育に関する教員の研修機会や、必要な支援体制の整備が十分でないという現状が明らかになっています。
専門家の声
インクルーシブ教育の専門家である山田花子先生(仮名)は、「インクルーシブ教育は、障害のある子どもだけでなく、すべての子どもにとってより良い教育環境を実現するために不可欠です。多様性を尊重し、互いに学び合うことで、子どもたちは豊かな人間性を育むことができます。」と述べています。
未来への希望
双子の娘たちの卒業は、私にとって大きな喜びであると同時に、インクルーシブ教育の未来への希望でもあります。すべての子どもたちが、それぞれの個性や能力を活かし、共に学び、共に成長できる社会の実現に向けて、私たち一人ひとりができることを考えていきたいと思っています。
卒業式を終え、それぞれの新たな一歩を踏み出した娘たち。彼女たちの未来が、希望に満ちた明るいものでありますように。そして、すべての子どもたちが笑顔で過ごせるインクルーシブな社会の実現を願ってやみません。