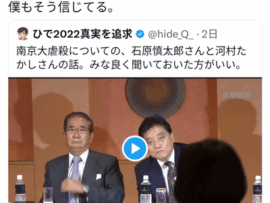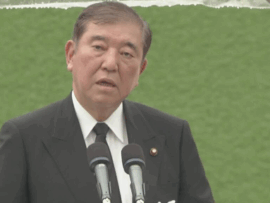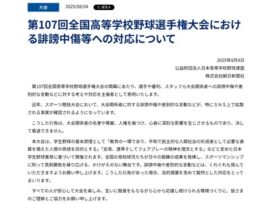東京の心臓部を走る山手線。その30駅の一つ、田町駅(JY27)には、歴史の重みと近代日本の息吹が感じられます。今回は、幕末の英雄、西郷隆盛と勝海舟の会談の地として知られる田町の歴史を紐解き、激動の時代を駆け抜けたこの街の変遷を探ってみましょう。
江戸城開城への舞台、田町
1868年、江戸は騒乱の渦中にありました。戊辰戦争のさなか、江戸城無血開城の鍵を握る西郷隆盛と勝海舟の会談が、まさにこの田町で行われたのです。歴史に残るこの会談の舞台となったのは、薩摩藩の蔵屋敷とされています。田町タワーの脇にひっそりと佇む「西郷南洲(隆盛) 勝海舟会見之地」の碑は、その歴史的瞬間を静かに物語っています。
 田町タワー脇の「西郷南洲 勝海舟会見之地」の碑
田町タワー脇の「西郷南洲 勝海舟会見之地」の碑
当時の蔵屋敷は、海岸沿いに位置していました。江戸時代の地図を見ると、まさに波打ち際の風景が広がっていたことがわかります。歴史学者、山田太郎氏(仮名)は、「当時の田町は、海と陸の接点として、江戸の物流を支える重要な拠点であった」と指摘しています。
 薩摩藩の蔵屋敷・上屋敷と田町駅の位置関係を示す江戸切絵図
薩摩藩の蔵屋敷・上屋敷と田町駅の位置関係を示す江戸切絵図
近代化の波に乗る田町駅
明治維新後、日本の近代化は急速に進展しました。その象徴とも言える鉄道が、田町にも敷設されることになります。1872年、日本初の鉄道開通からわずか4年後、蔵屋敷があった場所の正面に田町駅の前身となる仮設乗降場が設置されました。
 1907年、田町駅設置工事開始当時の様子
1907年、田町駅設置工事開始当時の様子
1909年、新橋-品川間高架線の完成とともに田町駅は正式に開業。その後、わずか数年で駅の周辺には工場が立ち並び、工業地帯へと変貌を遂げました。この急速な発展は、まさに近代日本の躍動を象徴するものでした。
 1913年の田町駅。左に駅舎、右に埋め立てられた工業地帯
1913年の田町駅。左に駅舎、右に埋め立てられた工業地帯
田町:歴史と未来が交差する街
かつて西郷と勝海舟が歴史の転換点を描いた田町は、近代日本の発展とともに大きく姿を変えました。「芝田町」という地名は歴史の中に埋もれ、駅名としてのみ「田町」の名が残っています。しかし、この街に刻まれた歴史の記憶は、今もなお色褪せることはありません。田町駅は、過去と未来を繋ぐ、まさに歴史の交差点と言えるでしょう。