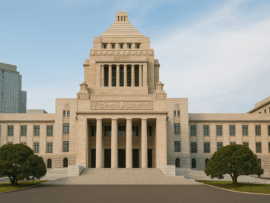[ad_1]
米国のトランプ大統領が3月下旬、次世代戦闘機「F47」の開発計画を発表した際の発言に波紋が広がった。戦闘機の同盟国への売却を巡り、同盟国に信頼を寄せていない姿勢をあからさまに示したためだ。
トランプ氏は自由貿易体制の解体にとどまらず、第2次世界大戦後に築かれた国際秩序そのものを変えようとしているのではないか――。各国が懸念するのは、大国が力にものを言わせて主導する世界の再来だ。
「相互関税」を打ち出した今月2日の演説で、トランプ氏は「米国は何十年もの間、略奪されてきた」と日本や欧州をやり玉に挙げた。同盟国・友好国も関係なく標的とした相互関税を目の当たりにし、トランプ氏が安全保障分野でも大なたを振るう事態に各国は身構える。
第2次大戦後、米国は自由主義陣営の盟主を自任し、国際秩序の構築を先導した。1991年に旧ソ連が崩壊すると、唯一の超大国となった。冷戦後、各国は軍事から経済や社会保障へ資源を回す「平和の配当」を享受してきたが、米国は防衛面の負担を一手に担わされ、不公平な扱いを受けてきたとトランプ氏はみる。
イスラエルの著名な歴史学者ユヴァル・ノア・ハラリ氏は、「国際秩序が今、崩壊しつつある」として、「弱肉強食」の時代への逆戻りを危惧する。
ハラリ氏は3月中旬に来日した際のイベントで、第2次大戦後に人類が繁栄したのは「強い国が一方的に小さい国を征服してはならないというルール」のためだと強調。ロシアのウクライナ侵略と、そのロシア寄りの姿勢を隠さないトランプ氏の復権によって、このルールが破られることへの危機感をあらわにした。
世界恐慌下の1930年代、米国は他国に高関税を課して貿易戦争を引き起こし、世界は大戦へと突入していった。当時との類似性も踏まえ、「世界は第3次大戦に向けた戦間期に入った」との指摘も出ている。
[ad_2]
Source link