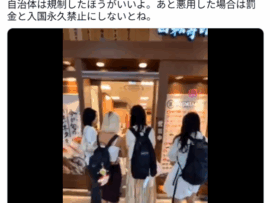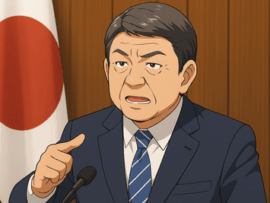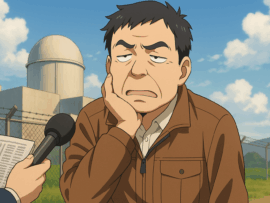人間の目は、単に「見る」ためだけにあるのではありません。5億年以上もの進化を経て、驚くべき機能を獲得してきたのです。この記事では、慶應義塾大学名誉教授・坪田一男氏の著書『「外にいる時間」があなたの健康寿命を決める』(サンマーク出版)を参考に、生命と光の神秘的な関係、そして人間の目が持つ知られざる能力について探求します。
生命の誕生と光の利用:25億年前の革命
生命は約37億年前に誕生し、地球の熱や化学エネルギーを利用して生きていました。しかし、約25億年前、シアノバクテリアという単細胞生物が登場し、光合成によってエネルギーを作り出す革命が起こりました。彼らは光をシグナルとして利用し、サーカディアンリズム(体内時計)を調整することで、エネルギー効率を高める術を身につけたのです。 生命にとって、地球の自転による昼夜のリズムは最も安定した環境変化であり、光への適応は生存に不可欠だったと言えるでしょう。
 シアノバクテリアの顕微鏡写真
シアノバクテリアの顕微鏡写真
目の進化:20億年の歳月
光を利用する生命にとって、光受容体の発達は重要なステップでした。約5億4300万年前のカンブリア紀には、ついに現在の目の原型となる器官が誕生します。驚くべきことに、目を持たない20億年の間に、生命は光情報を巧みに利用していたのです。東京海洋大学名誉教授・佐々木浩氏も、原始的な生物における光受容体の進化について、多くの研究成果を発表しています。
人間の目:9つの光受容体と驚異の機能
人間は9つの光受容体を持っています。そのうち4つは視覚に関わる視覚型光受容体、残りの5つは視覚以外に作用する非視覚型光受容体です。視覚型光受容体は、色覚や明暗感知など、私たちが「見る」という行為に直接関与しています。一方、非視覚型光受容体は、体内時計の調整やホルモン分泌、さらには気分や睡眠にも影響を与えていることが近年の研究で明らかになってきています。例えば、メラノプシンと呼ばれる非視覚型光受容体は、青色光に強く反応し、体内時計のリセットや覚醒レベルの向上に重要な役割を果たしています。
赤色を見分ける能力:生存戦略における進化
人間を含む霊長類は、赤色を感知する能力に長けています。これは、熟した果実や血液を識別する上で、生存に有利に働いたと考えられます。果実を見つけることで栄養を確保し、怪我の出血を早期に発見することで生存確率を高めることができたのです。京都大学霊長類研究所の研究でも、霊長類における色覚の進化と食性との関連性が示唆されています。
まとめ:光と生命の神秘
人間の目は、単に外界を認識するだけでなく、生命維持や進化にも深く関わわっています。光を感知し、利用する能力は、生命の誕生から現在に至るまで、進化の過程で重要な役割を果たしてきたのです。現代社会においても、光環境を整えることは、健康維持に欠かせない要素と言えるでしょう。