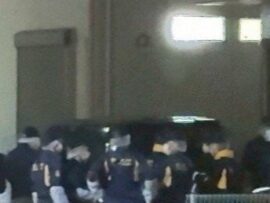日本がパリ五輪で総合3位という輝かしい成績を収めた背景には、国民に深く根付いた部活動文化がある。その成功モデルは、少子高齢化が進む韓国にとって大きなヒントとなるだろう。本稿では、部活動の意義と、それがいかに日本のスポーツ界を支えているのかを紐解き、韓国スポーツの未来についても考察する。
部活動:未来のアスリートを育む土壌
約20年前、ある日韓戦での経験が今も鮮明に記憶に残っている。相手チームの投手は球速よりも緩急を巧みに操り、堅実な守備で失点を許さない。まさに「堅固さ」と「忠実」を体現したチームだった。彼は部活動で野球に打ち込んだと話していた。1880年代に始まった部活動は、まさに草の根スポーツの象徴と言える。

日本の部活動参加率は中学生で70.6%、高校生でも52.7%と非常に高い。彼らは授業後、1~4時間もの練習に励み、週末には練習試合や地域大会に参加する。この地道な活動が、日本のスポーツの底力を支えているのだ。
部活動と学業:好循環を生み出す相乗効果
部活動は学業の妨げになるどころか、むしろプラスに作用するという意見もある。20年前の日本人投手も「勉強と部活動は互いに良い関係」だと語っていた。ソウル大学体育教育科のキム・ユギョム教授は、「部活動は勝利に驕ることなく、敗北を受け入れる人間性教育から始まる。大谷翔平選手のようなスター選手も部活動で人格を形成した」と説明する。

キム教授はさらに、規則的な運動が脳の老廃物を取り除き、認知能力を向上させるという研究結果も発表している。部活動を通じて運動を日常とすることで、生活スポーツへの意識も高まり、結果として選手層の拡大と深化につながるのだ。
学校スポーツの活性化:韓国スポーツの未来
韓国も日本と同様に少子高齢化社会に直面し、選手資源の減少が課題となっている。パリ五輪で韓国は総合8位と健闘したが、メダル獲得は射撃、フェンシング、アーチェリーなどに偏っていた。一方、日本のメダルは7種目に分散し、陸上やり投げやバスケットボール、バレーボールでも好成績を収めた。この差はどこから来るのか?

大韓体育会のユ・スンミン会長は就任後、「学校スポーツの活性化と種目の均等発展、生活スポーツの進化」を掲げた。これは、パリ五輪でのメダル偏重と、日常的なスポーツ活動の低迷を認識した上での発言と言えるだろう。パク・セリ、パク・テファン、キム・ヨナ、ソン・フンミンといったスター選手は偶然生まれたのではない。しかし、彼らのような特別な才能を持つ選手が再び現れるとは限らない。だからこそ、学校スポーツと生活スポーツの普及が重要となる。
韓国体育大学のホ・ジンソク教授は、「生活スポーツとエリートスポーツは上下ではなく、並んで走る車輪のような関係。学校体育はこの二つを連結する軸となるべきだ」と強調する。部活動は、生活スポーツとエリートスポーツの橋渡し役を果たし、「在野の名手」を発掘する場となる。そこから特級選手が育ち、エリートスポーツシステムへと導かれる。そして、スポーツを通じた国のソフトパワー向上にも繋がるのだ。
部活動:持続可能なスポーツ文化の創造
日本の部活動は、スポーツ文化を根底から支える重要な役割を担っている。韓国もこの成功モデルを参考に、学校スポーツの活性化に取り組む必要がある。部活動の普及は、未来のアスリート育成だけでなく、国民の健康増進や地域社会の活性化にも貢献するだろう。そして、スポーツを通じた国際交流や文化発信にも繋がるはずだ。