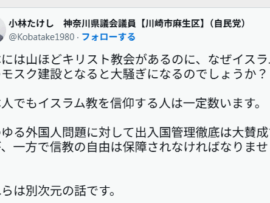日本では少子高齢化が深刻化する中、社会保障制度の維持が大きな課題となっています。特に現役世代の社会保険料負担の重さが問題視されており、負担軽減策が求められています。中には、社会保障の財源を消費税に一本化するという案も出ていますが、果たして私たちの負担は軽くなり、手取りは増えるのでしょうか?この記事では、データに基づいてその実態を検証し、現役世代の未来について考えていきます。
社会保障の財源:保険料と税金の現状
社会保障の財源は、現役世代が負担する社会保険料だけでなく、消費税や赤字国債などの税金も投入されています。国立社会保障・人口問題研究所の「社会保障費用統計」(2022年度)によると、総費用153.0兆円のうち、社会保険料は77.3兆円(被保険者40.7兆円、事業主36.6兆円)、税金等は64.2兆円、その他11.5兆円となっています。つまり、社会保険料は約半分を占めるものの、残りは税金等で賄われているのが現状です。
 2022年度の社会保障費用統計
2022年度の社会保障費用統計
社会保障給付費137.8兆円のうち、医療、年金、介護といった社会保険給付は115.8兆円(全体の84.0%)を占めています。保険料だけで賄われているわけではないため、純粋な「保険」とは言い難い側面があります。
現役世代への負担集中:社会保険料vs消費税
社会保険料は基本的に賃金に比例するため、現役世代の負担が大きくなっています。各世代の社会保険料負担額を見ると、25歳から64歳までの現役世代の負担が、65歳以上の高齢世代を上回っています。例えば、55~59歳世代の負担額は70歳以上世代の3.5倍、24歳以下でも1.5倍と、大きな世代間格差が存在します。
一方、消費税は全ての世代が負担する税金です。世帯主の年齢別に見ると、65歳以上の高齢世代も44歳以下の現役世代と同等かそれ以上の負担をしていることが分かります。これは、「消費税は薄く広く負担する社会保障財源として適切」という主張の根拠となっています。
食生活アドバイザーの山田花子さん(仮名)は、「現役世代の負担軽減は喫緊の課題です。社会保障制度を持続可能なものにするためには、消費税を含めた税制全体の改革、そして社会保障給付の見直しも必要でしょう」と指摘しています。
消費税増税で負担軽減は実現するのか?
社会保障財源を消費税に一本化する案では、確かに社会保険料の負担は軽減される可能性があります。しかし、消費税は低所得者層ほど負担感が大きいという問題点も抱えています。本当に現役世代の負担軽減につながるのか、慎重な議論が必要です。
まとめ:未来への展望
少子高齢化が進む中、社会保障制度の持続可能性は、私たちにとって重要な課題です。社会保険料、消費税、そして社会保障給付、それぞれのバランスをどうとっていくのか。現役世代の負担軽減と、高齢者の生活保障を両立させるためには、多角的な視点からの議論と、未来を見据えた改革が不可欠です。