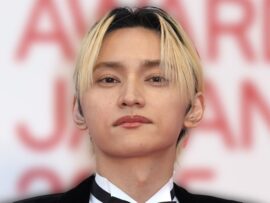日本の未婚率と少子化は深刻な社会問題となっています。家族を持たない人が増え、情緒の安定を得にくい状況が広がっています。フランスの社会学者デュルケムも、人は社会的な生き物であり、集団に属することで情緒の安定を得ると述べています。家族はまさにその基盤となる存在であり、幸福度に大きな影響を与えます。
未婚者と既婚者の幸福度の格差
世界価値観調査(2017~2022年)によると、日本の25~54歳の未婚者で「あまり/全く幸福でない」と回答した割合は19.2%であるのに対し、既婚者は6.6%でした。未婚者の幸福度が低い傾向は世界共通ですが、日本では男女でその傾向が逆転している点が特異です。
男性の未婚者は幸福度が低い
主要5カ国を比較すると、男性はどの国でも未婚者の幸福度が低い傾向にあります。特に日本ではその差が顕著で、未婚男性の37.8%が「あまり/全く幸福でない」と回答しています(既婚男性は9.2%)。
 alt
alt
日本の既婚女性は幸福度が低い?
一方、女性では日本だけが既婚者の幸福度が低いという結果が出ています。これは他国では見られない日本の特徴です。家事分担の不均衡など、伝統的な性役割分業が影響している可能性が考えられます。料理研究家の山田花子さん(仮名)は、「女性が家事の負担を大きく感じていることが、幸福度を下げている一因ではないか」と指摘しています。
離婚と自殺の相関関係から見えるもの
離婚率と自殺率の推移を見ると、男性では正の相関、女性では負の相関が見られます。離婚は男性にとって自殺のリスクを高める一方、女性にとっては逆に保護要因となる可能性を示唆しています。これは、結婚生活が女性にとって負担となっている側面があることを示しているのかもしれません。
家事分担の不均衡が未婚化・少子化を加速?
厚生労働省の人口動態統計によれば、日本の離婚率は上昇傾向にあります。家事分担の不均衡が解消されない限り、未婚化・少子化に歯止めをかけることは難しいでしょう。経済支援だけでなく、結婚を経ずに子どもを産み育てやすい環境整備も必要です。社会学者の佐藤一郎さん(仮名)は、「社会全体の意識改革と、子育て支援の拡充が不可欠だ」と強調しています。
まとめ
日本の未婚化・少子化は、家事分担の不均衡など、根深い社会問題と密接に関係しています。真の幸福を追求するためには、個人の意識改革だけでなく、社会全体の構造改革が求められています。