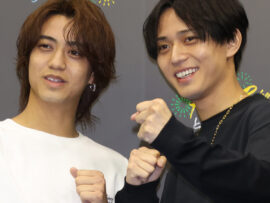1923年9月1日、関東地方を襲った未曾有の大災害、関東大震災。猛烈な揺れとそれに続く大火災は、東京を中心に甚大な被害をもたらしました。多くの人命が失われ、都市機能は麻痺し、人々の心に深い傷跡を残しました。この混乱の中、様々なデマが飛び交い、悲劇が悲劇を生むという悪循環が生まれました。朝鮮人虐殺事件はその代表的な例ですが、実はそれ以外にも、あまり知られていない重大事件が起きていたのです。今回は、角田房子氏のノンフィクション作品『増補改訂版 甘粕大尉』(朝日文庫)を参考に、その知られざる悲劇に迫ります。
未曾有の大地震と燃え広がる炎
午前11時58分44秒、関東一円を激しい揺れが襲いました。東京では138カ所から火災が発生し、瞬く間に市街地は火の海に包まれました。生き残った人々は、目の前の惨状に言葉を失い、精神的な平衡を失っていました。まるで平静を取り戻す暇を与えないかのように、余震は繰り返し襲ってきました。2日の正午までの24時間で、実に356回もの余震が記録されています。木造家屋が密集する市街地では、火災旋風も発生し、炎はさらに勢いを増して広がっていきました。
 関東大震災により崩壊した凌雲閣
関東大震災により崩壊した凌雲閣
麻痺した都市機能と孤立した東京
避難民や荷物が道路を埋め尽くし、消防車は思うように動けませんでした。水道管の破裂により消火栓は使用不能となり、電話も不通のため、命令や連絡もままならない状態でした。地震発生直後には、電信や電話などの通信機関が破壊され、鉄道も不通となりました。東京は、猛火に包まれながら、外部との連絡が完全に遮断され、孤立状態に陥ってしまったのです。唯一の連絡手段は、船橋の海軍無線電信所から紀州潮岬の無線電信局への無線電信のみでした。この情報が大阪に伝わり、ようやく関東大震災の惨状が外部に知られることになったのです。
地方への情報伝達と金沢憲兵隊の出動
地方で関東大震災の情報が伝わったのは、地域によってまちまちでした。当時、金沢憲兵分隊に所属していた中村久太郎氏(仮名)の証言によると、金沢憲兵隊が震災発生を知ったのは午後1時半頃だったといいます。中村氏を含む15、6名の兵士には、直ちに出動命令が下されました。「大地震により東京は壊滅状態」という情報を受け、米、味噌、乾パン、そして自転車を携え、救援活動のため東京へ向かったのです。当時の混乱と緊迫した状況を物語るエピソードです。料理研究家の山田花子さん(仮名)は、「非常時における食料の備蓄の重要性を改めて認識させられる出来事」と語っています。

デマと混乱、そして知られざる悲劇
関東大震災は、自然災害の恐ろしさを改めて私たちに突きつけると同時に、非常時における情報伝達の重要性、そしてデマの危険性を浮き彫りにしました。混乱の中で生まれたデマは、人々の不安を増幅させ、悲劇的な事件を引き起こす要因となったのです。この教訓を胸に刻み、防災意識を高めるとともに、正確な情報に基づいて行動することの大切さを改めて認識する必要があるでしょう。