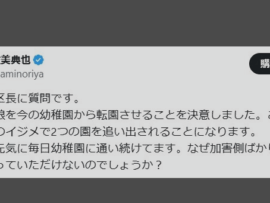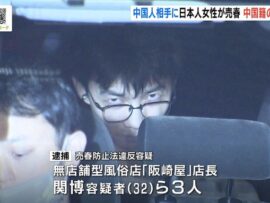[ad_1]
御上先生を熱血教師にしなかった理由
2025年1月から3月まで放送され、反響を呼んだTBSドラマ「御上先生」。官僚を主人公に据え、学校教育や教育行政が抱える課題を取り上げながら「生徒に考えさせる」教師の姿を描き、冬ドラマの総合視聴率トップに輝いた。固定観念を覆す学園ドラマが生まれた背景や現代日本の教育の課題とは何か。脚本家の詩森ろば氏と、元文部科学省の寺田拓真氏の対談の後編をお届けしよう。前編はこちらから。
──これまで学園ドラマといえば、熱血教師や型破りの教師が熱く語りかけ、生徒を力強く導いていくスタイルが主流でした。
詩森 最初は、私たちもそうした作品を作ろうと思っていたんです。でも、寺田さんと、ドラマの学校教育監修をしていただいた工藤勇一先生から「有名な学園ドラマがテレビで放送されると学校が荒れる」とお聞きしまして。熱血教師がわーっと話すドラマはカタルシスを感じて気持ちいいのですが、私たちもアップデートしなければと思い、生徒に考えさせる方向に変えました。
寺田 私は2021年から1年間、ミシガン大学教育大学院の修士課程に留学したのですが、アメリカでも「学園ドラマが教育課題の解決を阻害している」という論文がありまして。学園ドラマは「アウトサイダー(または熱血)教師がやってきて、生徒に施しをして成功に導く」となりがち。施す、施されるという構図の指導で生徒は自立できるのか疑問が残ります。また、学園ドラマは受験戦争に勝つというハッピーエンドになりがち。だからこそ、「御上先生」が学習指導要領や教科書に切り込んだ意味は大きいと思います。
──「御上先生」は学習指導要領をめぐる課題やヤングケアラーなど、社会や学校のリアルが多く盛り込まれていましたね。
詩森 個と政治がつながる問題については、日頃からアンテナが張っている方だと思います。演劇では多岐にわたる作品を描いてきましたし、引き出しもそれなりにあります。また、このドラマが視野に入った頃から、文科省や教育に関するドキュメンタリーなどは意識して観るようにしました。
その中で「生徒が文科省に対して個人的な憤りを感じているとしたら教科書検定のことを書けるかもしれない」「裕福な生徒が通う私立校だからこそ、貧困に踏み込んだら問題の根深さを伝えられるのでは」と扱うコンテンツをピックアップしました。教科書検定の是非については国際情勢も含めて結論は出ていませんから、テレビドラマでこうですと言ってしまうのは危険です。私もわからないことがあるし、社会観や歴史観をはらんでいますし。だからこそ、ドラマを見た1人ひとりが調べて考えてみほしいと思っていました。
[ad_2]
Source link