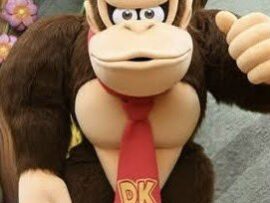9日、衆議院内閣委員会における日本学術会議法に関する質疑の中で、日本維新の会の三木圭恵議員が「会員の選出方法」について質問した。
【映像】ヤジ→「ヤジに答えないで」→「委員長も注意していただけます?」国会紛糾
三木議員は冒頭「現在の日本学術会議の会員の選出は現会員が次の会員を指名するいわゆるコ・オプテーション方式が採用されているが、この採用方法が学術会議の中の一部の思想の固定化につながってきたのではないかという疑念が生じてきている」と述べた上で北海道大学教授の宇山智彦会員の発言を引き合いに出して以下のように質問した。
「宇山会員は『この法律が通ることによって予想されるのは、コ・オプテーションが一旦途切れて、その後これまでとは違う人が入ってくる。(中略)特に文系の中の人には理系の人以上に政府にすり寄る、そして、政府だけでなく、かなり右の方に立っている人たちが少数ではありますが確実にいます。そういう人たちがここに入ってくると思います。そういう状態を許していいのかということも考える必要がある』というご発言をしている。宇山会員が何をもって“右の方に立っている人”と認識を持っているかは知らないが、明らかに自分とは違う考え方、“右の方に立つ人間”を排除しようという意図を持って発言されていることは明白に感じることができた。この発言から、今まで自分たちの思想信条と同じ人をコ・オプテーションで選んできたと、自分たちとは相入れない思想信条の人は日本学術会議の会員にはさせないという強い意志が感じられると思う」
「また、宇山会員は2023年4月20日の新聞赤旗に寄稿して『学術会議は学術会全体の声を政府に届けられる唯一の公式の機関です。その活動が制約を受ければ、今以上に学問的根拠のない政治が行われる可能性が高まります』と述べている。そもそも、学術会全体の意見というならば、右の立場の人も左の立場の人もいて当然だと思うが、この宇山会員の発言が、現在の学術会議が一方に偏った学者で構成されているのではないかという危惧を国民に与えるものだと私は思う」
「Facebookで(宇山会員は)発言した意図について『学術会議は現在は政府と協力しつつ独立した立場を保てる研究者が会員になっているが、法人化後には右派が入って学術会議の活動を政治化する可能性があるのではないか』と説明した。かなり偏った考えを持っていると思う。そう疑問視する理由として(宇山会員は)『学術会議の法人化を中心的に唱えてきたのは、日本会議や旧統一協会とつながりのある政治家であり、その人々が自分たちと同じ政治的立場を持つ人を学術会議の会員にしようと考えていても全くおかしくないからである』というような発言をしている。制度として新しい法案になると、このような政治家が自分たちと同じ政治的立場を持つ人たちを学術会議の会員にすることができるのか?」
これに対し坂井大臣は「(宇山会員が)どうしてこの発言をしたかというと、この方が今までは右に立つ人が入っていなかったけれども今度からはダイバーシティを確保する選考方法であるので、いろんな方が入ってくる。逆に言うと、ダイバーシティ確保に向けて適切な選考方法だということをこの方がご評価いただいているということかと思う」とここまで述べると議場内で笑い声が響いた。
坂井大臣は続けて「こういった形で公正公平に幅広く日本の知恵を結集する選考方法を知恵を出して考えてきたし、これを計画通り運用し、結果を出すため努力をしていきたいと思う」と述べた。
三木議員は「左派であろうと右派であろうと、私はやはりいろいろな方々が入ってきて学術に関して研究・究明をしていくことは必要だと思っている。ただ、やはり左派の方とか右派の方が政治的に中立ではないというのは『いかがなものかな』と思っている。この方(宇山会員)は続けて『現在の学術会議に関しては、共産党に連なるような左派の存在は全く感じられない。学術会議の外での法人化反対運動が軍学共同反対運動とかなり重なっていることもあり、学術会議もそのイメージで見られがちだと指摘した。一方、過去の学術会議では共産党系などの左派の会員が政治的な主張や活動をしていたとして、けっして好ましいことではなかったとした上で、法人化後の学術会議に右派が入ることも同様に好ましくないとした』としている。私はこれを読み、あくまでも過去にという限定ではあるが、宇山会員は共産党系の左派の会員がいて、政治的な活動をしていたと認めていると思う。『過去にあったが現在にはない』というこの主張は私は違っていると思っており」
とここまで話すと議場内に低い声のヤジが響いた。三木議員がその方向に顔を向けると大岡敏孝委員長が「ヤジに答えないでください。質問を続けてください」と促した。
三木議員がヤジの方に「すいませんけれども、ヤジは控えていただけますでしょうか。ちゃんと議会運営委員会でちゃんと結論を出して」と話すと大岡委員長は「政府に対する質疑を続けてください」と指摘。
三木議員はこれに「はい」と応じながらも「すいませんけど、委員長も注意していただけます?」と要望を出し、大岡委員長は「ご静粛に願います」と注意した。
三木議員は「あくまでも過去にという限定ではあるが宇山会員は共産党系の左派の会員がいたということを認めている。私は今も現実的にやはりそういった方々がいるということを後でまた質問する。このコ・オプテーションによって過去が現在の会員選定に連なってきているということは事実なので、過去にあったが現在にはないというこの主張に私は矛盾を感じている。法改正が行われた後、一旦途切れたコ・オプテーション方式が再度採用されることによって、また政治的な中立が阻害されることがあるのではないかと危惧するが見解を伺う」と質問した。
これに坂井大臣は「会員の選定で大切なことは、客観的かつ透明性を確保しつつ国民に説明できる方法で選考されること、会員が仲間内だけで選ばれる組織だと思われないために外部に説明できる選考の仕組みを整えることが必要であると指摘をされている。この法案においては、透明化と多様性について、まず選考に先立って学術会議が作成する選定方針の中で、今後6年間の活動を見据えた新会員の専門分野を設定することとしている。分野や選考の固定化・既得権化の抑止の必要性は懇談会の報告書でも指摘をされているところで、次に、法学・政治学などの専門分野ごとに業績を審査する分野別業績審査委員は割り当てられた人数より多い候補者を選考して、その中から会員候補者選定委員会が人選することとしている。会員候補者選定委員会が選定した候補者と総会の選任との関係も同様だ。要するに、実質的に絞り込みを2回行うことで、狭い範囲で選ばれた人たちがそのまま会員に選任されてしまわないように設計している。海外のアカデミーはいずれもこのような実質的な意味のある投票を行って絞り込んでいる。また、この選任の過程を国民に明らかにすることも条文化しており、このように選考プロセスを客観性・透明性の高いオープンなものにすることで、会員選考の自立性、コ・オプテーションの要請を前提としつつ、分野の固定化の防止などが図られるものと考えている」と答えた。
三木議員は「今行われてるコ・オペテーション方式と、今後法改正が行われて後のコ・オプテーション方式とは若干方式が違って、二重に審査をして、優れた研究または業績があって人格が高潔であり、かつ会議の業務などにちゃんと遂行できる方を会員として選んでいくということになっていくと理解した。コ・オプテーション方式が1つの考え方に凝り固まったような、連綿と続く思想の固定化みたいなものにつながらないように配慮していただきたい」と述べた。
日本学術会議の組織改革法案は9日の内閣委員会で採決され、与党に加えて、日本維新の会が賛成に回ることで、原案のまま可決する見通しだ。
(ABEMA NEWS)
ABEMA TIMES編集部