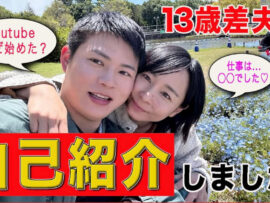NHK大河ドラマで生田斗真さん演じる一橋治済はどんな人物だったのか。歴史評論家の香原斗志さんは「8代将軍吉宗の孫で、一橋家の第2代当主。10代将軍家治の跡継ぎ問題の中で主導権を握り、息子家斉が11代将軍になったことで幕政に隠然たる影響力を持った」という――。
■自殺未遂者がでた10代将軍家治の後継者問題
田沼意次(渡辺謙)の前で、ついあくびが出てしまった10代将軍徳川家治(眞島秀和)は、「すまんな、お鶴と夜更かしをしてしもうた」と語り、意次は「お励みのこと、なによりにございます」と答えた。NHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢〜」の第19回「鱗の置き土産」(5月18日放送)
お鶴とは、大奥総取締の高岳(冨永愛)が連れてきた、家治の亡き正室にそっくりな女性、鶴子(川添野愛)のこと。嫡男の家基(奥智哉)を失い、自分の血を引く後継がいなくなった家治だが、鶴子とのあいだに実子をもうけようと思い立ったのだった。
そこに急使が「上様、主殿頭様(意次のこと)、ご無礼仕ります」といって駆け込み、「先ほど西ノ丸にて、知保の方様が毒をあおられた由、上様に宛ててこちらが」と告げ、手紙を差し出した。家治の側室である知保の方(高梨臨)は、手紙におおむね次のようなことを書いていた。
———-
このたび京都から、亡き御台所によく似た中臈(ちゅうろう)を迎えたと聞いたが、結果、実の子ができれば、自分は徳川には無用の人間となるので、上様と自分の子で、いまは亡き家基のもとに行きたい――。
———-
■吉宗が残した因縁
同じタイミングで、家治の養女になっている種姫(小田愛結)の母、すなわち田安徳川家の創始者である宗武の未亡人と、その息子で種姫の兄の松平定信からも、家治にいまから実子が生まれても種姫を娶るには年齢差が大きいので、種姫の年齢に見合う養子をもらってくれ、という願いが届けられた。
また、地保の方は一命をとりとめ、毒をあおったのは狂言だった可能性が浮上する。
この状況を受けて、家治は意次に「もう実の子は、あきらめたいということじゃ」と告げた。意次は「同じ徳川とはいえ、上様の血をまったく受けぬ者が将軍を継ぐのでございますぞ」と強く諭すが、家治は「じつのところ余の血をつなぐのが、怖いところもある」といって、身体不自由だった父、9代将軍家重の血を継承していくことへの不安を述べた。
家治は「ふたを開けてみれば、後を継げるような男(おのこ)はあの家にしかおらぬ」という。「あの家」とは、吉宗の四男(三男が早世したので事実上の三男)の宗尹(むねただ)が創始し、その嫡男の治済(生田斗真)が当主の一橋家である。家治は、吉宗が秀でた宗武や宗尹を避け、身体も言語も不自由な家重に将軍の座を継がせたことによる因縁を断ち切るために、養子をとりたい旨を述べた。
そして「次回予告」では、一橋治済が「次の将軍には当家の豊千代を」と語るのが流された。
■すべては一橋治済の思惑通りに
では、この後、史実はどう展開するのか。天明元年(1781)、家治は世継ぎ選びを田沼意次に命じている。その結果、選ばれたのは一橋治済の嫡男、豊千代だった。
実際、一橋家の最大のライバルである田安家は、賢丸すなわち定信が白河松平家の養子に追いやられたのちに、その兄で病弱だった治察が死去したため、しばらく当主が不在の状態にあった。家治が第19回で語ったように、後継ぎは「あの家(一橋家)にしかおらぬ」状況だったのである。
「べらぼう」では、家治の次の将軍に内定していた嫡男家基の早すぎた急死は、治済が手を回した毒殺であるかのように描かれた。その設定は脚本家の創作だが、そこから多くのことが、治済に有利な方向に進んでいったことはたしかだ。
天明6年(1786)8月、家治はにわかに病に倒れ、そのまま死去する。こうなると、家治の信用が厚かった意次は、治済にはもはや邪魔な存在である。すぐに老中を罷免され、領地や屋敷も次々と没収された。こうした決定を主導したのは御三家および御三卿だが、なかで主導権を握れたのは、次期将軍の父である治済だった。