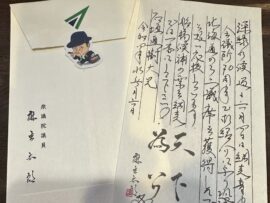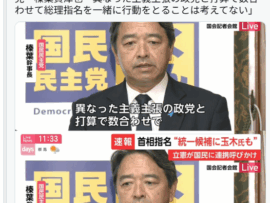高温多湿となる梅雨から夏にかけての時期は、細菌による食中毒のリスクが特に高まります。身近な食材にも危険が潜んでおり、中には感染後に手足の麻痺を引き起こす難病につながるケースも報告されています。この時期に注意すべき食中毒の原因と、その効果的な予防法について解説します。
じめじめ暑い時期に食中毒が増える理由
気温と湿度の上昇は、腸管出血性大腸菌O157などの細菌が繁殖しやすい環境を作り出します。食中毒の原因は細菌だけでなく、ウイルス、寄生虫、自然毒、化学物質など多岐にわたりますが、梅雨から夏にかけては特に細菌性食中毒の発生件数が増加する傾向にあります。秋にはきのこや山菜による自然毒、冬にはノロウイルスといったように、季節によって注意すべき原因が異なります。
食中毒を防ぐための「3つの原則」と実践
健康検定協会理事長の望月理恵子氏によれば、病原性大腸菌O157のように、細菌は室温で数十分のうちに倍増することが分かっています。食中毒を防ぐためには、「細菌を付けない」「増やさない」「やっつける」という3つの基本原則が重要です。
「付けない」ためには手洗いや調理器具の洗浄・使い分けを徹底し、「増やさない」ためには食品を早く調理して食べたり、適切に冷蔵・冷凍保存したりします。購入時は生鮮食品を最後に選び、寄り道せず持ち帰ってすぐに冷蔵庫へ。そして、「やっつける」手段の基本は、十分な加熱や消毒です。細菌は食品の購入から調理、保存、食事、後片付けまで、あらゆる過程で付着・増殖する可能性があるため、各段階での注意が必要です。
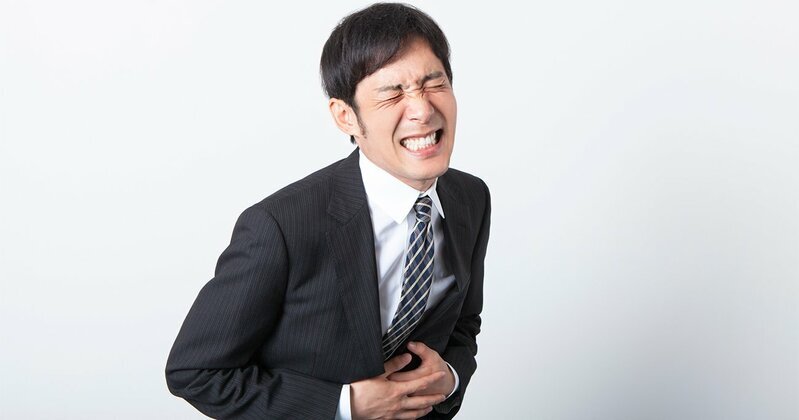 高温多湿時期の食中毒対策における食品の取り扱いイメージ
高温多湿時期の食中毒対策における食品の取り扱いイメージ
鶏肉の加熱不足に要注意:難病「ギラン・バレー症候群」のリスク
特に注意が必要な食材の一つが鶏肉です。食中毒の原因菌であるカンピロバクターは、鶏の腸管に常在していることが多く、加熱が不十分な鶏肉を食べることによって感染するリスクがあります。カンピロバクターは十分な加熱によって死滅させることが可能で、食品の中心部を75℃以上で1分間以上加熱することが一般的な目安とされています。
もし感染した場合、数週間後に「ギラン・バレー症候群」という自己免疫疾患を引き起こすことがあります。これは、感染をきっかけに運動神経が障害され、手足の麻痺などの症状が現れる難病です。リハビリ病院などで栄養指導を行う日本臨床栄養協会評議員の遠藤惠子氏も、こうした患者に時折出会うと指摘しています。
高温多湿の時期は、細菌性食中毒の危険性が高まります。特に鶏肉の加熱不足はカンピロバクター感染、ひいてはギラン・バレー症候群につながる可能性もゼロではありません。食中毒を防ぐためには、「細菌を付けない、増やさない、やっつける」という基本を徹底することが何より重要です。食材の適切な取り扱いや十分な加熱を心がけ、安全に梅雨から夏を過ごしましょう。
参考:https://news.yahoo.co.jp/articles/d406474de4afde1b7a7b8e39dc8f3fa780ad9aa3