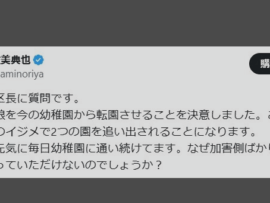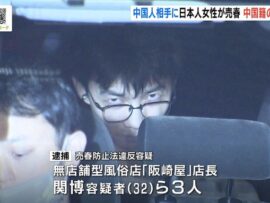現在、全国で進められている都市再開発事業の約8割が、完了時期の延期や費用の増加といった問題に見舞われていると、日本経済新聞が今年3月下旬に報じました。それ以降、JR中野駅前の中野サンプラザの再開発計画白紙撤回をはじめ、後楽園など東京都内から、茨城県取手市や岐阜県岐阜市など地方都市まで、計画変更や見直しのニュースが相次いでいます。これらの事態は、資材価格の高騰と人手不足による費用増加が主な原因とされており、多くのメディアはこれを「ゆゆしき事態」として報じています。しかし、本当にこれは危機的な状況なのでしょうか。むしろ、人口急減が進む日本において、時代にそぐわない拡大・膨張型の都市再開発のあり方を見直すべき天の配剤と捉え、立ち止まるべき時なのかもしれません。進行中の再開発事業は、このままでは将来の不良資産となるか、あるいは周辺地域を疲弊させるかのどちらかになるリスクをはらんでいます。さらに、このような将来的な「お荷物」となりかねない事業に、私たちの税金である莫大な自治体や国の補助金が投じられている現状を知る必要があります。以下に、日本の都市再開発のシステムとその問題点を詳述し、これらの事業が人口減少時代にいかに不適合であるかを明らかにします。
再開発事業が進みやすい背景とその仕組み
まず、都市再開発事業は、一般的なマンションの建て替えに比べて着手までのハードルが低いという特徴があります。分譲マンションの建て替えに必要な所有者全体の5分の4以上の賛成に対し、都市再開発法では地権者の3分の2以上の同意で事業を進めることが可能です。これは、再開発事業が「公共性」の高い事業であると法的に位置づけられているためですが、3分の1が反対しても強行できる点は注目すべきでしょう。
それでも、地権者全体の3分の2という同意率は決して低くありませんが、実際には多くの再開発計画で賛成が集まりやすい傾向にあります。その背景には、「持ち出しなし」で事業が進められるという地権者側のメリットが大きいことが挙げられます。都市再開発事業は、建物を高層化することで新たに生み出される「保留床」と呼ばれる床面積を売却し、そこから得られる利益を建設費に充当することで成り立つ仕組みです。このため、地権者は自己負担をほとんど負うことなく、高層化された新しいビル内の「権利床」を取得・入居できます。自身でビルや住宅を建て替えるよりも経済的な負担が少ないため、「得だ」と判断する地権者が多いのです。
事業拡大と隠されたコスト:タワマンと補助金
「保留床」を創出して事業費を捻出することが前提となるため、現在の都市再開発事業のほとんどはタワーマンション建設とセットになっています。これは、多くの床面積を生み出し、それを販売することで大きな利益を得られるディベロッパーにとって、非常にメリットが大きい事業形態です。さらに、行政側にもメリットがあります。新しい高層ビル内に役所機能を低予算で移転できたり、入居者やテナント増加による一時的な固定資産税などの税収増が見込めたりするためです。
日本の都市再開発現場のイメージ画像:進行中の高層ビル建設プロジェクト
しかしながら、実態としては「保留床」の売却益だけで地権者の「持ち出しなし」を実現することは困難です。都市再開発事業は前述の「公共性」を建前としているため、国の補助金や自治体からの助成金が多額に投入されており、場合によっては事業費の半分近くが公費で賄われているケースも存在します。住宅が余り始める人口減少時代において、住宅供給を増やす拡大・膨張型の事業に、多額の公的な補助金が投じられている現状は、公共性という名のもとに実質的な税金投入が行われていることを意味し、その適否が問われなければなりません。
まとめ:再開発の遅延・費用増大を機に見直すべき
資材価格高騰や人手不足による日本の都市再開発の遅延や費用増加は、表面的な問題であると同時に、現在の再開発システムが抱える根本的な課題を浮き彫りにしています。それは、人口減少という時代の潮流に逆行するかのような拡大路線、将来的に不良資産となりうる空間の創出、そしてそれを税金で支えるという構造的な問題です。今回の再開発プロジェクトの躓きを単なる「ゆゆしき事態」と捉えるのではなく、多額の公費を投じて進める都市開発のあり方を、人口減少が進む日本の国土全体の未来を見据え、抜本的に見直す好機とすべきです。
参照元:Yahoo!ニュース (出典元の記事リンクを記載)