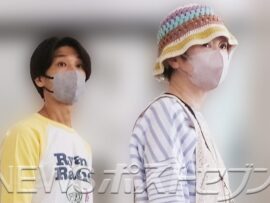中国の政治情勢において、習近平国家主席を取り巻く権力構造に微妙な変化の兆候が見え始めている。最近の軍部高官の解任や、故李克強元首相に対する異例の追悼記事掲載といった一連の出来事が、水面下で進行している可能性のある権力闘争や指導部内の動揺を示唆している。日本でも関心が高い隣国の動向として、これらの動きは注目に値する。
軍部における異変の兆候
権力変化の兆候はまず軍部から表面化した。6月27日、全国人民代表大会(全人代)常務委員会は、習主席に近いとされる苗華・中央軍事委員会委員の罷免を決定した。さらに、習主席の腹心と見られていた李漢軍・海軍参謀長も全人代代表職を解かれた。続く6月30日、中国中央テレビが報じた政治局集団学習の様子では、4カ月間動静が伝えられていない何衛東・副主席を除く中央軍事委員会委員全員が出席するという異例の光景が見られた。これには、董軍国防相や邱楊・中央軍事委員会公務処理庁副主任、王成男政治工作部副主任も同席している。これらの動きは、自殺説も取り沙汰されている何宏軍政治工作部常務副主任だけでなく、昨年10月に習主席の視察に随行していた方永祥公務処理庁主任の失脚を示すものだという解釈が出ている。軍内部における「習近平派の排除」がまだ完了していないことを示唆する措置だとの見方もある。
 中央軍事委員会幹部(張又侠、方永祥ら)を伴い軍部隊を視察する中国の習近平主席
中央軍事委員会幹部(張又侠、方永祥ら)を伴い軍部隊を視察する中国の習近平主席
李克強元首相追悼記事とその波紋
軍部の動きに続き、7月3日には党機関紙「人民日報」が、昨年死去した李克強元首相の生誕70周年を追悼する長文の記事を掲載し、中国国内の世論に波紋を広げた。記事は李氏を「真実を語り、実用を追求する業務スタイルを先導し、形式主義・官僚主義に反対した」と評価した。この表現は、現指導部が不利な統計を隠蔽するなど非実用的だという批判とも読み取れる部分が含まれていた。人民日報は「亡くなった国家指導者の誕生日を周期的に記念する規定に伴う記事」だと注釈を付けたものの、読者の間では故人が生前、習主席と対立関係にあったことや、胡錦濤・温家宝政権時代の比較的自由な統治スタイルが意図的に強調されていると受け止められた。
今後の焦点:北戴河会議
過去1年間、水面下で静かに、しかし激しく繰り広げられてきた権力闘争は現在も進行中である。来月初めに開催されると予想される北戴河での非公式会合(北戴河会議)では、反習近平派と習主席勢力の間で、下半期の第20期中央委員会第4回全体会議(4中全会)の議題や日程、そして習氏の今後の地位などを巡る最終的な交渉が行われると見られている。
専門家による分析と今後の展望
韓国外国語大学国際地域研究センターのカン・ジュンヨンセンター長は、習近平体制の権力移譲説が事実であれば、「退陣の根拠を健康上の理由に挙げる可能性が最も大きい」と分析している。また、「さまざまな兆候を総合すると、習氏に対する最終処理は1981年11期6中全会を通じて『毛沢東の業績を7対3の功過論』と評価した鄧小平の過去清算方式を参考にし、政治的混乱と権力闘争的な性格を最小化する『秩序正しい退陣』方式に従う可能性が高い」との見方を示した。
さらに踏み込んだ評価は米国からも出ている。7月2日付の米時事誌ナショナル・インタレストのブランドン・ワイチャート上級編集委員は、「中国共産党がリーダーシップを根本的に変えようとしているのは誰の目にも明らかであり、それは実質的に生存が危うくなったためだ」と指摘し、今年の秋には政権交代が起きうるとまで予想した。中国のエリート層は習主席が危機の原因だと信じており、脅威を除去するために迅速に動いている、との見解を述べている。
ビジネス調査会社ストラテジー・リスクスのアイザック・ストーン・フィッシュ最高経営責任者(CEO)は6月30日、ソーシャルメディア上で「習近平の真の状態を把握することは難しい」とした上で、ウィンストン・チャーチルの「(中国と似たロシアの)クレムリン政治はじゅうたんの下で繰り広げられるブルドッグの戦いと同じで、外からは唸り声だけしか聞こえず、骨が外に出てきて初めて誰が勝ったのか知ることができる」という過去の発言を引用した。これは、安易な論争ではなく、さまざまな状況に備えておく時期が来たという主張である。
結論
最近の中国における軍部人事を巡る動きや、故李克強元首相に対する異例の追悼記事は、習近平政権内部で何らかの変化や緊張が生じている可能性を示唆している。これらの兆候は、来月に予定されている北戴河会議で、今後の中国の指導体制や方向性について重要な議論が行われることを予感させる。複数の専門家が指摘するように、現在の状況は予測困難であり、今後の展開を慎重に見守る必要がある。