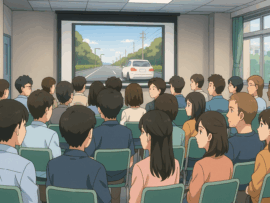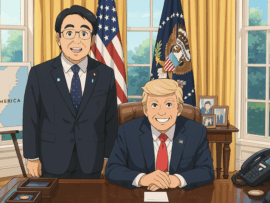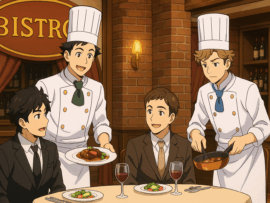現在、日本の食卓に欠かせない米の価格が高騰しており、その原因として中間業者や転売業者の存在を指摘する消費者の声が少なくありません。小泉進次郎農林水産相もまた、米の流通実態を「不透明」「ブラックボックス」と問題視し、実態解明に向けた調査に乗り出しています。しかし、米の流通現場からは、こうした見方に対し「根本原因は全く別のところにある」との異論が上がっています。
現場の声:米不足こそが原因
東京近郊で長年米店を営む店主、中村真一さん(仮名)は、米価格高騰の理由について断言します。「なぜ、米が高いのか? 米不足が根本の原因ですよ」。中村さんは、現在政府が行っている小売業者などの米の在庫量調査について「流通の目詰まりや、特定の業者が価格をつり上げていると言いたいのだろうが、全く矛先が違う」と指摘します。記者が昨年来、様々な米関連の関係者から話を聞く中で、農林水産省以外からは一貫して「米不足こそが高値の原因」との声を聞いてきたと言います。
政府の見解と流通調査
これまでの国会や記者会見などで、小泉農水相は米の流通構造について繰り返し言及してきました。例えば、6月1日には「5次卸とか5次問屋とかあまりにも多い」、6月5日には「『他の食料品に比べ、米の流通は極めて複雑怪奇、ブラックボックス』と指摘が寄せられている」と発言しています。こうした問題意識に基づき、農林水産省は6月17日、国に届け出ている全ての米の出荷・販売業者に対し、6月末時点の在庫量の報告を求める調査を実施すると発表しました。この調査結果は7月下旬に公表される予定です。
流通の現実:大手スーパーの力
しかし、中村さんのような流通現場の人間から見ると、政府の今回の調査は効果が薄いものに映ります。米穀安定供給確保支援機構の今年5月の調査によると、消費者が米を購入する場所として最も圧倒的なシェア(55.8%)を占めているのはスーパーです。特に大手スーパーは、最終的な消費者米価の価格形成において強い影響力を持っています。
 スーパーの米売り場に並ぶ米袋。消費者米価の価格形成力を握る大手スーパーの流通チャネルを示す。
スーパーの米売り場に並ぶ米袋。消費者米価の価格形成力を握る大手スーパーの流通チャネルを示す。
中村さんは、厳格な原価管理を行う大手スーパーの流通経路には「中間マージンで利益を上げる中小の卸や問屋が入り込む余地は全くない。入りたくても無理な話だ」と説明します。大手との取引は規模や効率が重視され、従来型の中小業者が介在しにくい構造があるためです。
直接取引の広がりと在庫の意義
中間業者を挟まない動きは、米店のような小規模な販売店でも広がっています。中村さん自身もその一人で、20年以上前から農家との直接取引を増やしてきました。自身の倉庫に保管されている米は、買い占めではなく、新米が入荷するまでの間、顧客に継続的に販売するための不可欠な在庫であると強調します。
調査の意図への疑問
こうした流通現場の実情を踏まえ、中村さんは政府の調査の背景にある意図に疑問を投げかけます。「結局、国は『流通業者が米価格高騰の悪者だ』というストーリーにしたいのだろう」。米不足という根本原因から目を逸らし、特定の業者や流通経路に責任を押し付けようとしているのではないか、というのが現場からの見方です。
結論
米の価格高騰は、消費者の家計を圧迫する喫緊の課題です。政府は流通の不透明性を問題視し、在庫調査によって原因を特定しようとしています。しかし、米の生産・流通に携わる現場からは、「圧倒的な米不足」こそが真の原因であり、現在の流通構造、特に大手スーパーが支配的なチャネルにおいては、伝統的な中間業者が価格を釣り上げる余地は限定的であるとの指摘が強く出ています。今回の政府調査が、異なる立場からの意見をどのように踏まえ、真の価格安定に繋がる対策を導き出せるか、今後の動向が注目されます。
参照:
https://news.yahoo.co.jp/articles/ce2ac8ff7c885613c94f496dc8675953c44acf3a