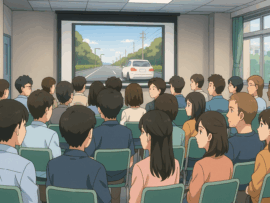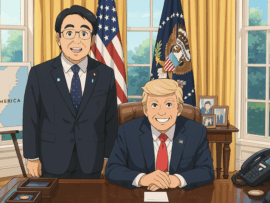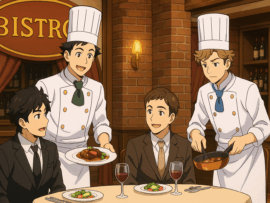周囲に話があちこちに飛ぶ人がいるかもしれません。そのような人は、驚くほど創造的な発想を持つ天才である可能性があります。一見奇妙に思えるその発言は、脳が多様な要素を拾い上げているからです。最新の研究は、本人さえ気づいていない脳の秘密、特にADHD(注意欠陥・多動性障害)と創造性の関連性をひも解いています。
型破りな創造性を示すADHDの子どもたち
ある実験では、ADHDの子どもを含むグループに様々なおもちゃを見せた後、「今までにない新しいおもちゃを考えてほしい」と依頼しました。短時間で革命的なアイデアが生まれることを期待したわけではなく、研究者が着目したのは、既に見せたおもちゃを真似るのではなく、独自のアイデアを出せるかという点でした。既存の例を見てしまうと、それに囚われて創造性が阻害されることが知られています。しかし、真にクリエイティブな人は前例に囚われず、それを無視できるはずです。
その結果、ADHDの子どもたちは既成概念にとらわれずに考えることができ、見たばかりのおもちゃをコピーすることなく、独自の提案をしました。つまり、より創造的だったのです。これらの実験は、ADHDの人が少なくともブレインストーミングの分野において、子どもでも大人でもより創造的であることを示唆しています。では、彼らの脳内で何が起きているのでしょうか。
何も考えていないようで活発な「ぼんやり脳」
椅子にもたれてリラックスし、特定のことを考えずに思考を流れるままに任せてみてください。今日あったこと、夕食のメニュー、明日の天気など、様々なことが頭に浮かぶでしょう。このようにぼんやりしている時、脳全体が休止しているわけではありません。実は、脳内のあちこちの部分が連携して形成される「デフォルト・モード・ネットワーク(Default Mode Network=DMN)」が活発になっているのです。
DMNは、脳が特別なタスクを実行していない時に活発になるネットワークで、「ぼんやり脳」とも呼ばれます。このDMNが、「意識の流れ(stream of consciousness)」と呼ばれる自発的な思考の流れを生み出すと考えられています。例えば、「ランチは寿司よりラザニアが食べたいな」「リビングの壁紙はもう少し暗い方がよかったかも」など、心の中で自分と対話している時に活発になります。しかし、上司からメールを書くよう頼まれるなど、能動的な行動に移るとDMNの活動は抑えられ、今度は脳の実行機能を司る「タスク・ポジティブ・ネットワーク(Task Positive Network)」が活動を始めます。メールを書いている間は、計画や衝動の制御を司る部分が活発になるのです。
 脳の活動と創造性のイメージ
脳の活動と創造性のイメージ
気を散らす「ぼんやり脳」こそ創造性の源泉
脳の実行機能を司るタスク・ポジティブ・ネットワークは、通常、デフォルト・モード・ネットワークと同時に活性化しません。実行機能がオンになるとDMNはオフになり、実行機能に場を譲る必要があります。もし両方が同時に活発であれば、メールを書いている最中も気が散って集中できなくなるでしょう。
ADHDはまさにこのような状態です。メールを書こうと決めてもDMNがオフにならず、実行機能と同時に活発なままです。場を譲ろうとせずに邪魔をするかのように機能します。脳の「ぼんやりプログラム」をオフにするボタンが鈍いかのようです。DMNという名称は、単にぼんやりするという行為に科学的な名前をつけただけのように思え、何の役にも立たないと思う人もいるかもしれません。なぜ進化は、このようにぼんやりして集中の邪魔をする機能を脳に組み込んだのでしょうか?
しかし、話はそう単純ではありません。DMNは、名前だけかっこよくて集中の邪魔をするだけでなく、まさに創造性の源となる自発的な「アイデアの流れ」を生み出しているのです。ADHDの脳に見られる、気を散らす特性とも関連するこのDMNの活発さが、型破りな発想やひらめきにつながっていると考えられています。
参考資料
- アンデシュ・ハンセン 著, 久山葉子 訳. 『多動脳 ADHDの真実』