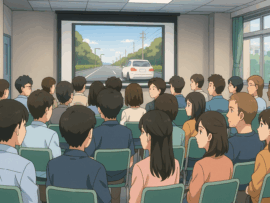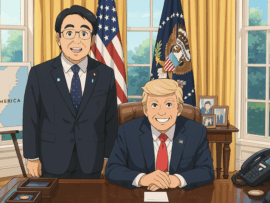2017年7月、奥秩父の山中で1泊2日の予定で登山に出かけた60代女性から連絡が途絶えました。大雨が降りしきる中、彼女は一体どこへ向かったのか。警察などの公的機関による懸命な捜索もむなしく、行方は掴めないまま捜索は打ち切りとなりました。その後、夫と3人の息子たちから依頼を受け、民間の山岳遭難捜索チームLiSS代表の中村富士美氏とメンバーが現地に赴きました。山岳遭難捜索のリアルな様子を、中村氏の著書『「おかえり」と言える、その日まで 山岳遭難捜索の現場から』から一部抜粋し、その知られざる真実をお伝えします。
山岳遭難捜索の拠点と家族の想い
私たち民間捜索隊はすぐに装備を整え、奥秩父の現地へと向かいました。山梨県側の登山道につながる林道の入り口では、遭難されたYさんのご家族と地元消防団の団長が待っていてくださいました。林道の終点には山小屋があり、Yさんが1日目の登山を終えて宿泊した場所です。この小屋が、捜索期間中、私たち民間捜索隊とご家族の滞在場所となりました。消防団長は毎日、ご家族が宿泊する民宿から山小屋まで、送迎をしてくださいました。
 山岳遭難における道迷いのイメージ、山の危険性
山岳遭難における道迷いのイメージ、山の危険性
70代のご主人と、40代から30代の3人の息子さんたちは、現地の民宿に泊まり込み、捜索を見守っていました。ご家族はほとんど登山経験がないにも関わらず、未だ見つからない母を探したい一心で、登山靴を購入し、日々独自の捜索活動を行っていたのです。日中は長男が民宿に残り、次男と三男が山に入って無線でやりとりをするという体制でした。
家族参加の光と影:二次遭難のリスク
遭難者のご家族が捜索への参加を希望することは珍しくありません。自宅でじっと待っている辛さに耐えられない、一刻も早く家族を見つけたいという切実な想いが、ご家族を現場へと向かわせます。捜索に参加することがご家族の精神的な安定につながることは確かです。
 奥秩父で遭難したYさんの予定登山ルート図 – 山岳遭難捜索の現場
奥秩父で遭難したYさんの予定登山ルート図 – 山岳遭難捜索の現場
しかし、ご家族の二次遭難の危険性は否定できません。後で聞いた話ですが、Yさんの次男と三男が捜索の最中に登山道から外れてしまい、だんだん元の場所が分からなくなってしまったこともあったといいます。ご家族の二次遭難を防ぐため、どの時点で「捜索は私たちに任せてください」と申し出るかも、専門の捜索隊に求められる重要な判断の一つとなります。
ご主人は、民宿から山小屋に着くと、まずYさんの名前を大声で呼ぶのが日課でした。その声は山びことなって、捜索中の私たちの耳にも届きました。妻の安否が心配でたまらない状況にも関わらず、「体力的に山を歩くことはできないから」と捜索隊員に気を遣ってくださり、捜索から戻ると毎回冷やしたオロナミンCを差し入れてくださいました。
 奥秩父の登山道入り口付近、道迷い現場の様子 – 季節による変化と捜索の難しさ
奥秩父の登山道入り口付近、道迷い現場の様子 – 季節による変化と捜索の難しさ
捜索の現実と家族の絆
この奥秩父の山岳遭難事例は、民間捜索チームが直面する現実と、遭難されたご家族の筆舌に尽くしがたい苦悩、そして深い絆を示しています。公的な捜索が打ち切られた後も、家族は諦めずに自らの足で探し続け、民間チームはプロの視点と技術で捜索を継続します。捜索の現場は、ただ行方を探すだけでなく、残された家族の精神的なケア、そして何よりも安全を確保しながら進めなければならないことを改めて示唆しています。無事の帰りを願う家族の切実な声は、山に響き渡り、捜索隊員たちの心にも重く響きました。
参考文献: