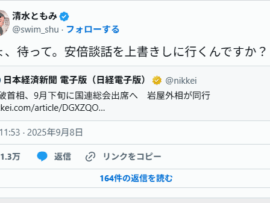2023年10月7日の出来事を発端とするイスラエルとイスラム組織ハマスの軍事衝突は、ガザ地区に甚大な被害をもたらし、今なお停戦交渉は難航しています。この複雑で長期にわたる紛争について、パレスチナ側はどのような立場を取り、何を訴えているのでしょうか。本稿では、国際ジャーナリスト山田敏弘氏による駐日パレスチナ常駐総代表部ワリード・シアム大使へのインタビューに基づき、パレスチナ側から見たこの衝突の「現実」と「本音」に迫ります。イスラエル側の見解と比較しつつ、歴史的背景、国際法における抵抗権、そして平和に向けた展望について、大使の言葉から紐解きます。
 駐日パレスチナ常駐総代表部 ワリード・シアム大使の肖像、ガザ地区を巡る状況についてインタビューに応じる
駐日パレスチナ常駐総代表部 ワリード・シアム大使の肖像、ガザ地区を巡る状況についてインタビューに応じる
過去に根差す現在の現実:占領の歴史
ワリード・シアム大使は、2023年10月7日の出来事だけが注目されることへの疑問を呈し、現在の状況を理解するためには必ず歴史を知る必要があると強調します。大使によれば、パレスチナ人は長期間にわたるイスラエルによるパレスチナ領土の軍事占領を経験してきました。イスラエル国家の成立以前、ヨーロッパから移り住んだ人々が、イギリス委任統治下のパレスチナでジェノサイドや虐殺を行った歴史があり、それは今日まで続いていると述べています。かつてイギリスが「テロリスト集団」と呼んだ集団が、現在のイスラエル国防軍となったという見解を示し、この軍隊によるパレスチナ領土の軍事占領が70年間続いていることが紛争の根源にあると訴えました。
抵抗権と国際法の解釈
パレスチナ人が抵抗するたびに「テロリスト」と呼ばれる状況に対し、シアム大使は国際法によって占領下の住民にはいかなる形であれ抵抗する権利が与えられていると主張します。ジュネーブ条約や国連決議、人権に関する文書は、軍事占領下にある人々が抵抗する権利を持つことを認めているため、パレスチナ人の抵抗は正当な権利の行使であると位置づけます。一方で、イスラエル側が自らの行動を「自衛」と呼ぶことに対し、軍事占領下にある人々は国際法上、占領国に対する自衛権を持たないという法の支配を指摘しました。大使は、パレスチナ人の抵抗運動の歴史において、常に攻撃の対象は軍事占領軍であり、民間人を殺害したことは一度もないと述べています。パレスチナ側は、イスラエル人であろうとパレスチナ人であろうと、いかなる民間人の殺害にも反対の立場であることを改めて表明しました。
外交と平和への展望、そして国際社会の役割
現在の状況下では、イスラエル側との良好なコミュニケーションは困難になっているとシアム大使は語ります。しかし、外交においては誰とでも話を続ける必要があり、個人的な関係とは切り離して対応していると述べました。過去には元イスラエル大使たちと個人的に親しく、いかに決定的な平和に到達するか、いかに二国家解決を実現するかについて話し合っていた経験を振り返り、以前の状況との違いを強調しました。日本政府を含む多くの国が支持する二国家解決こそが、パレスチナ問題の恒久的な解決策であるとの考えを改めて示しました。大使は、現在約150カ国がパレスチナ国家を承認しており、パレスチナは国連に加盟していることから、日本がパレスチナ国家を承認するための全ての基準を満たしているとし、日本による承認への期待を表明しました。現在のガザ地区では5万5000人以上が犠牲になっていると述べ、人質解放とハマス掃討を目的としたイスラエル軍の作戦が長期化している状況に対する懸念を示しました。停戦交渉が続いているものの、事態は依然として複雑であり、国際社会の積極的な関与が不可欠であるとの認識を示唆しました。
結論
駐日パレスチナ常駐総代表部のワリード・シアム大使へのインタビューは、イスラエルとパレスチナの紛争に対するパレスチナ側の深い歴史認識と、国際法に基づく抵抗権の主張を浮き彫りにしました。大使は、現在の衝突は単なる偶発的な事件ではなく、70年にわたるイスラエルによる軍事占領という歴史的文脈の中で理解されるべきであると力説しました。国際法における占領下の住民の権利と、イスラエルの「自衛」との間の矛盾を指摘しつつ、パレスチナ側が常に軍事占領軍を標的としてきた歴史を強調し、民間人犠牲への反対を明確にしました。最終的に、大使は平和への道として二国家解決の重要性を再確認し、日本を含む国際社会によるパレスチナ国家承認への期待を表明しました。このインタビューは、ガザ紛争という複雑な問題の背景にある歴史、法的な論点、そしてパレスチナ側が描く解決への道を理解する上で、重要な視点を提供しています。
参考文献:
https://news.yahoo.co.jp/articles/a65b84e6c7feb2f60004a68299f5cd266d123942