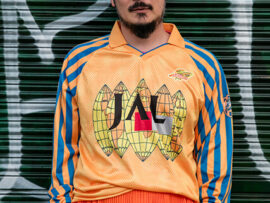物価高騰への対策が間近に迫る参院選の主要な争点となる中、家計の消費支出に占める食費の割合を示す「エンゲル係数」への関心が高まっています。2024年にはこの係数が43年ぶりの高水準に達し、多くの人々からは家計の苦境を象徴する指標との声が聞かれます。日本銀行も利上げ判断における重要な材料として、この係数の推移を注視しているとされています。しかし、専門家の中には「統計調査に歪みがあり、実態を正確に反映していない可能性がある」との指摘も少なくありません。
物価高とエンゲル係数の実態
総務省の家計調査によると、2024年に2人以上の世帯が消費に費やした月平均額は30万0243円で、物価変動を除いた実質ベースでは前年比1.1%の減少となりました。その一方で、急速な円安の進行が輸入コストを押し上げたほか、人件費や資材費の上昇も相まって、食品価格の改定が相次いでいます。帝国データバンクの調査によれば、主要な食品メーカーが昨年値上げした商品は合計で1万2520品目にも上りました。
その結果、エンゲル係数は前年比0.5ポイント増の28.3%となり、これは1981年以来の高さです。本年に入ってからも、コメの価格高騰などを背景に、この係数は依然として高い水準で推移しています。
エンゲル係数とは:歴史的変遷とその意義
エンゲル係数は、19世紀のドイツの統計学者エルンスト・エンゲルによって提唱された指標で、家計の金銭的な余裕度を測るものとされています。食費は生活に不可欠であり、削減しにくい支出であるため、その割合が大きくなると、衣料品や娯楽といった他の出費が圧迫されます。このため、通常は所得が低いほど係数は高くなり、反対に所得が増えれば係数は低くなるとされてきました。日本では1970年時点で34.1%だった係数が、豊かな中間層の拡大に伴い長期にわたって下落を続け、2005年には22.9%にまで低下していました。
「生活苦」だけではないエンゲル係数上昇の背景
しかし近年、エンゲル係数は再び上昇傾向に転じ、年間ベースで「生活苦の目安」とされる3割に迫っています。実質賃金が伸び悩む中で食費が膨らむ現状は、多くの人々が負担を感じていることの表れであることは間違いありません。
とはいえ、大和総研の矢作大祐主任研究員は、「係数の上昇が必ずしも日本人の困窮を示しているとは限らない」と指摘します。その理由の一つが、日本社会における高齢化の急速な進展です。子供が独立し教育費の心配がなくなった高齢世帯では、少々高価でも質の良いものを食べたいと考える傾向があるため、エンゲル係数は上昇しがちです。
 物価高騰が続く中、スーパーマーケットの精肉コーナーで食料品を選ぶ人々。日本のエンゲル係数上昇の背景にある家計の負担増と消費行動の変化を象徴する一枚。食費と消費支出の関連性を示す。
物価高騰が続く中、スーパーマーケットの精肉コーナーで食料品を選ぶ人々。日本のエンゲル係数上昇の背景にある家計の負担増と消費行動の変化を象徴する一枚。食費と消費支出の関連性を示す。
さらに矢作氏は、「海外の事例を見ても、女性の社会進出の加速は食費の増加につながりやすい」と述べています。仕事と家事の両立に忙しい共働き世帯では、外食の頻度や、割高な総菜など「中食」の購入回数を増やす傾向が見られます。これらの社会構造の変化も、係数上昇の一因となっていると考えられます。
家計調査の「歪み」:統計精度への疑問符
野村証券の岡崎康平チーフ・マーケット・エコノミストは、「家計調査の回答には歪みがあり、エンゲル係数が実態を正確に反映できていない可能性がある」との見方を示しています。この調査は基本的に夫婦のどちらかが世帯全体の収支を回答しますが、最近では夫婦間で財布を別々に管理するケースが一般化しています。これにより、配偶者の収支を正確に把握していない状況が目立ち、調査回答から抜け漏れした支出が増えている可能性が指摘されています。つまり、支出総額が実際よりも過小に計上されることで、日常的な支払いが把握しやすい食費の割合が見かけ上高く算出されてしまう、という問題が生じているのです。
シンクタンクのNIRA総合研究開発機構が以前、エコノミストを対象に経済統計に関する評価アンケートを実施したところ、日本銀行短観や貿易統計など計23の景気動向指標の中で、最も点数が低かったのがこの家計調査でした。有効サンプル数が少ない上に、記入作業が煩雑になることから、世帯によって回答の精度にバラつきが出やすいとされています。また、すべての支出を包み隠さず明かすことへの心理的抵抗感から、誠実な回答ではない場合があることも課題です。
政府・日銀の注目と今後の改善策
しかしながら、国内総生産(GDP)の計算にも用いられる重要な統計であることには変わりなく、物価高の局面において、政府や日本銀行の関係者も家計調査から導き出されるエンゲル係数に強い関心を寄せています。
野村証券の岡崎氏は、「統計の精度を高めるために、調査のオンライン化を一段と推進すべきだ」と提言しています。さらに、「調査内容を簡略化する一方で、サンプル数を増やした新たな統計を国が用意し、家計調査を補完するのも効果的だろう」と述べており、統計の信頼性向上に向けた具体的な改善策の必要性を訴えています。
参考文献
- 総務省 統計局:家計調査
- 帝国データバンク:主要食品メーカーの値上げ動向調査
- 大和総研:主任研究員のコメント
- 野村証券:チーフ・マーケット・エコノミストのコメント
- NIRA総合研究開発機構:経済統計に関する評価アンケート