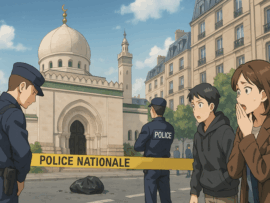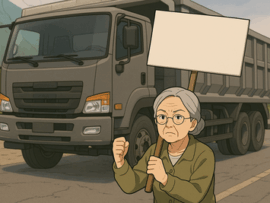「小4の壁」などに代表される学童保育の利用困難は、多くの共働き家庭が直面する課題です。さらに、次に待ち受けるのは長い夏休みをどう乗り切るかという「夏休みの壁」。友だちとの予定が合わない、昼食を一人で取ることになる、家での留守番が増えるなど、子どもの長期休暇中の過ごし方は親にとって毎年頭を悩ませる問題です。子どもがこの夏休みを有意義かつ安全に過ごすためには、どのような計画や心構えが必要なのでしょうか。民間学童保育「キッズベースキャンプ」を運営する東急キッズベースキャンプ代表取締役社長の島根太郎氏に、その具体的な対策とヒントを聞きました。
増加する共働き世帯と「学童の壁」の現状
夏休みが目前に迫り、その過ごし方に頭を悩ませる親は少なくありません。近年、働く女性の増加は著しく、日本の女性の労働力率を示す「M字カーブ」は著しく浅くなり、もはや「台形」に近づいています。これにより共働き世帯が増加し、小学生が放課後や長期休暇中に利用する「放課後児童クラブ」(一般的に「学童」と呼ばれる)の登録児童数は全国で151万9952人、待機児童も1万7686人と、利用希望者の増加に伴い待機児童も増加傾向にあります(こども家庭庁「令和6年 放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)の実施状況」〈2024年5月1日時点〉より)。
 夏休み計画を立てる共働き家庭の親子。タブレットを見ながら相談する様子。
夏休み計画を立てる共働き家庭の親子。タブレットを見ながら相談する様子。
特に、保育園から学童へ移行する際の「小1の壁」や、学童の対象年齢から外れることもある「小4の壁」に直面し、希望しても学童を利用できない家庭や、子どもが学童に行くことを嫌がるなどの理由で、今年の夏休みは「学童なし」で過ごす予定の家庭もあるでしょう。
「学童なし」家庭を支える!地域施設の活用術
「お子さんが学童に通っていない場合、一般的な代替手段として活用できるのは、地域の放課後子ども教室や児童館です」と、島根氏は指摘します。さらに、「図書館や公民館、夏休み期間中は小学校の体育館・校庭や図書室などの施設が開放されることもあるため、これらを上手に活用することも有効な選択肢です」と提案します。
放課後子ども教室は、すべての小学生児童を対象として、自治体が地域住民と連携し、学習支援や遊び、体験活動などを行う子どもの居場所を提供する事業です。また、児童館では、夏休み期間中に子どもが「孤食」とならないよう、持参したお弁当を館内で食べることができるスペースを設けているところもあります。こうした地域の子どもの居場所は、親が仕事中の子どもの安全と健全な過ごし方をサポートする重要な役割を担います。
夏の猛暑対策も兼ねた安全な居場所探し
近年、全国的に真夏日や猛暑日が続き、屋外で長時間遊ばせることによる熱中症のリスクが懸念されています。このような気候条件を考慮すると、屋内での活動が可能な居場所の確保はより一層重要となります。子どもの健康と安全を守るためにも、今回挙げられたような自宅近くで利用できる公共施設について、改めてその利用条件や開放状況を事前に確認しておくことが非常に大切です。
共働き家庭にとって、小学生の長い夏休みは大きな課題ですが、地域には様々なサポート体制が存在します。これらの代替施設を積極的に活用し、子どもたちが安全で充実した時間を過ごせるよう、早めの情報収集と計画的な準備を進めることが、「夏休みの壁」を乗り越える鍵となるでしょう。
参照元: Yahoo!ニュース