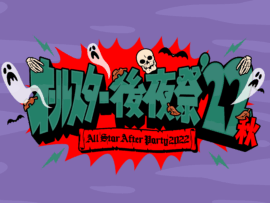2019年7月23日、米国側が当初要求していた25%から10%低い15%で決着した日米間の自動車関税交渉は、電撃的な合意として世界に報じられました。当時の安倍晋三首相は「相互関税について25%まで引き上げるとされていた日本の関税率を、15%にとどめることができました。これは対米貿易黒字を抱える国の中で、これまでで最も低い数字となる」と述べ、日本の成果を強調しました。
この突然の合意の裏側には何があったのか。キヤノングローバル戦略研究所上席研究員の峯村健司氏が、その詳細と戦略を深く掘り下げて分析します。
交渉成功の評価と合意の背景:トランプ流交渉術と「コメ」の存在
峯村氏がまず注目したのは、ホワイトハウス高官がSNSに投稿した交渉中の写真でした。そこには、ドナルド・トランプ大統領(当時)の手元に置かれた書類があり、日本の米国への投資額が「4000億ドル」から「5000億ドル」へと手書きで書き換えられている様子が鮮明に写し出されていました。
峯村健司氏はこの修正について、「元々4000億ドルという数字を日本側が出し、それに対しトランプ大統領が『それでは少ない。自動車の関税を1%下げてほしいならこれを出せ』と要求し、たまたまそこにあったペンで5000億ドルと書き直したもの」と解説しました。さらに、「元々不動産の方なので、家の値切りと一緒ですよね、そこは。やり方としては」と、トランプ氏の交渉スタイルを不動産取引に例えて分析しました。
この15%での決着は、日本にとって「よくやった」と言える結果だと峯村氏は評価します。「もし8月1日という期限に間に合わなければ、もっととんでもない関税をかけられている可能性もあったので、そういう意味では、今回15%とはいえ、そこで収まって良かった」と述べ、最悪のシナリオを回避できた点を強調しました。また、トランプ大統領が「TACO(Trump Always Chickens Out)」したわけではなく、「タフな交渉をした」という姿勢を見せたかったための投稿だったと指摘しました。
なぜこのタイミングでの合意に至ったのか。その鍵は、日本の国内事情、特に「コメ」にありました。日本が自動車関税の引き下げを求める一方、トランプ氏は「コメ」を不平等の象徴と見て、その関税引き下げを強く要求していました。しかし、当時の日本は参議院選挙を控えており、与党である自民党にとって農家票の確保が不可欠でした。そのため、選挙期間中はコメに関する交渉を保留するよう求めていました。選挙が終わり、コメというカードを切れるようになったことで、自動車関税の引き下げ交渉も進展したというわけです。トランプ氏は、第一次安倍政権時(2006-2007年)の交渉でコメが盛り込まれなかったことを根に持っており、「日本はコメが足りていないのになぜ買わないのだ」と記者に語るなど、コメが日本の非関税障壁の象徴だと強く思い込んでいたとされます。
ホワイトハウス高官がSNSに投稿した日米貿易交渉中の写真。トランプ大統領が投資額「4000億ドル」を「5000億ドル」に手書きで修正している様子がわかる。
他国への影響と80兆円投資の真価:交渉を転換させた「切り札」
日米の合意は、当然ながら他国にも大きな影響を与えました。峯村氏の元にはEUや韓国の政府関係者から「どうなった?」との問い合わせが殺到したといいます。特に自動車を米国に輸出する韓国やEUから見ると、日本が有利になり、自国の自動車産業がさらに厳しい状況に置かれると懸念が募りました。元々円安が続いていたことで日本車は安く売れており、15%の関税が課されてもその影響を吸収できると考えられていたため、EUや韓国にとっては非常に厳しい現実となりました。
これまで8回にわたる日米交渉の中で、峯村氏は「3回目」の交渉が大きな転換点になったと指摘します。この時、ロバート・ライトハイザー通商代表(当時)との交渉は非常に険悪な雰囲気に包まれていました。ライトハイザー氏は特にコメの購入を強く主張しており、交渉の場に日本の農林水産省の担当者がいないことに怒りを見せたといいます。ライトハイザー氏の側近によると、この時点で交渉はほぼ決裂状態に陥っていたとのことです。
同時に、この日行われた安倍首相とトランプ大統領による45分間の電話会談も、険悪な状況だったと報じられています。トランプ氏が2回ほど怒ったとされ、安倍首相の長話や、トランプ氏にとって最も重要な政策である関税政策を否定する姿勢が、トランプ氏の不満を募らせた要因となりました。
しかし、この膠着状態を打開したのが、日本側から提案された「約80兆円の投資を行う」という巨大な投資パッケージでした。この提案がウィルバー・ロス商務長官(当時)に伝えられると、「それはいいじゃないか」と前向きな反応が得られ、交渉は再び動き出しました。
この投資は単なる一般的な投資ではありませんでした。中国が輸出規制を強化しているレアアースの分野で、日本と米国が手を携え、共同で開発を進めていくという内容が含まれていました。これにより、米国側は「じゃあ一緒にやろう」と交渉に乗り気になったのです。残りの細かい部分はゆっくり進めるという方針で合意に至りました。
この80兆円の投資と、それに伴う「利益の9割が米国に」という部分も注目されましたが、峯村氏はこの「9割」について誤解があることを明確にしました。「9割持っていくという意味ではなく、日本が投資した分の利益は日本もきちんと回収します。これは『利益の9割』というより、例えば米国にレアアースの会社ができて、そこで得られた売上は当然米国に還元されるという意味での9割」だと解説し、日本側も投資に見合う回収は可能であると強調しました。ただし、日本国内に建設されるはずだった工場などが米国に移ることで、日本の産業空洞化につながるリスクは依然として存在するとも指摘しています。
 日米貿易交渉の様子。トランプ政権下のタフな自動車関税協議を象徴する場面。
日米貿易交渉の様子。トランプ政権下のタフな自動車関税協議を象徴する場面。
結論:複雑な交渉の成果と今後の課題
2019年7月の日米貿易交渉における自動車関税15%での合意は、日本の外交努力と戦略的な提案が功を奏した結果と言えます。特に参議院選挙後の「コメ」カードと、中国に対する共同戦略としての「80兆円規模のレアアース関連投資」は、トランプ政権の要求を満たし、決裂寸前だった交渉を有利な方向へ転換させる決定的な要因となりました。
この合意は、日本の自動車産業が直面していた高関税リスクを回避し、一時的な安定をもたらしましたが、その裏でEUや韓国といった他国の自動車産業に影響を与え、また日本国内の産業空洞化という潜在的なリスクもはらんでいます。国際的な貿易交渉は常に複雑な要素が絡み合い、短期的な成果と長期的な影響の両面を考慮する必要があります。
参考文献
- FNNプライムオンライン. (2025年7月24日放送). 『サン!シャイン』. Source link: https://news.yahoo.co.jp/articles/4710ee800770643d86eafc79b814c10efda5339b