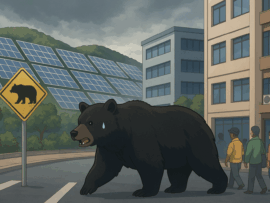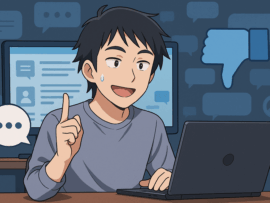2024年7月14日、ドナルド・トランプ元大統領が、対ロシア制裁の一環として、ロシアと取引を行う国に対し「二次関税」として100%の関税を課すと発表しました。これは、ウクライナ戦争を経済的に支える中国とインドを明確に標的とした措置です。これまでウクライナ侵攻に関して中立的な立場を維持してきた親ロ国インドにとって、この発表はまさに「不意打ち」であり、巧妙な「コウモリ外交」を展開してきたインド政府にとっては痛烈な報復となりました。
国際社会におけるインドへの高まる期待と現実のギャップ
2020年代に入り、インドは中国に代わる成長国として世界中の注目を集めています。人口では中国を上回り、AIや半導体といった重要な分野におけるサプライチェーン再構築の文脈においても、インドへの期待は日本国内でも急速に高まっています。安倍政権以降、日本はインドを安全保障上の重要なパートナーと位置づけ、中国に対抗し得る存在として意識する傾向が強まっています。
しかし、こうした世界的な期待の裏で、「インドは本当に中国の代替となり得るのか?」という疑問が、専門家の間で懸念として浮上し始めています。筆者は以前、2022年12月にダイヤモンド・オンラインに寄稿した記事『アップルがiPhoneをインドで生産、それでも「中国の代わり」になれない理由』において、産業面からインドが中国の代替になり得ないことを指摘しました。現在に至っても、当時提示した根本的な問題点は大きく改善された様子は見られません。
 インドのナレンドラ・モディ首相。彼のリーダーシップの下、インドの国際関係は複雑な局面を迎えている。
インドのナレンドラ・モディ首相。彼のリーダーシップの下、インドの国際関係は複雑な局面を迎えている。
専門家が指摘するインドの構造的な課題
米カーネギー国際平和財団のアシュリー・J・テリス氏は、2016年に発表した論文で「インドは超大国にはなれない」と明確に述べており、その理由を国家レベルの構造的な側面から詳細に論じています。彼の分析は、インドの政治的、経済的、社会的な内部要因が、その国際的な地位向上を阻害しているというものです。
さらに、最近発表された論文においても、テリス氏はこの主張を変えていません。彼は、インドが自らを大国と見なす「大国妄想」に陥っていると指摘し、その実態と国際社会における真の役割との間に大きな隔たりがあることを示唆しています。これらの専門家の見解は、インドへの過度な期待に対し、冷静かつ現実的な視点をもたらすものです。
まとめと日本の今後の関係構築
インドが直面する現在の国際情勢の厳しさ、そして長年指摘されてきた産業的・国家レベルでの構造的課題を鑑みると、現時点でのインドが真の「大国」として、また中国に完全に代わる存在として国際社会を牽引することは極めて困難であると言えます。特に、米国の「二次関税」のような予期せぬ外交的圧力は、インドのこれまでの立ち位置を揺るがす可能性があります。
日本は、安全保障を含む多角的な観点からインドとの関係を深化させる一方で、インドが抱える構造的な制約を正確に理解し、その実力を見極める必要があります。単なる「中国の代替」という期待値だけではなく、インドの真のポテンシャルと課題を見据えた、より現実的かつ戦略的な関係構築が求められています。
参考文献
- Ashley J. Tellis. “India: The Imperatives of a Leading Power”. Carnegie Endowment for International Peace. (2016).
https://carnegie-production-assets.s3.amazonaws.com/static/files/Brief-Tellis-India_Leading_Power1.pdf - Ashley J. Tellis. “India’s Great-Power Delusions”. Foreign Affairs. (2024).
https://www.foreignaffairs.com/india/indias-great-power-delusions