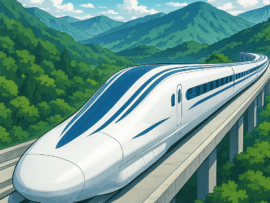「アメ車が売れないこの国」という認識がある一方で、日本の自動車文化、特にカスタムカーの分野には、独自の進化を遂げた熱いコミュニティが確かに存在します。先日開催された「37th MOONEYES Street Car Nationals®」は、その活気ある文化を象徴するイベントとなりました。単なる移動手段としての車を超え、個性と情熱を注ぎ込んだ「作品」として車を愛するオーナーたちが一同に会し、彼らのユニークな車に対する思いが浮き彫りになりました。本記事では、このイベントで出会った、車とともに生きる個性豊かな人々のストーリーに迫ります。
「整備士女子」ナナさんの半世紀前の相棒
車への深い愛情を実践する一人に、23歳の現役整備士、ナナさんがいます。彼女は19歳の時に、自身が生まれるよりも数十年前の1977年式シボレーC10ピックアップトラックを購入するという大胆な選択をしました。「私の名前がナナなので、ちょっと運命的にも思えました」と語る彼女は、整備士専門学校在学中からこの旧車に取り組み、エアコンの新設から配線の引き直し、さらにはエンジンの載せ替えに至るまで、そのほとんどの整備を自らの手で行いました。このC10は、彼女にとって手間もお金もかかったものの、「その過程も全部経験になりますし、このC10は自分にとって整備士キャリアの原点みたいな存在です」と、技術者としての成長を促したかけがえのない存在となっています。
 37th MOONEYES Street Car Nationalsに出展された、23歳の整備士ナナさんと彼女が自ら整備した1977年式シボレーC10
37th MOONEYES Street Car Nationalsに出展された、23歳の整備士ナナさんと彼女が自ら整備した1977年式シボレーC10
「新しい車に興味がない」20代男性の選択
北陸で家族と暮らす20代男性、リュウジさんの物語もまた、車の世代を超えた魅力を物語っています。彼の実家は車屋を営んでおり、幼少期からシボレーサバーバンやアストロ、ハマーH2といったアメ車に囲まれた環境で育ちました。「家の敷地いっぱいに、もはやパズルゲームみたいに並んでいますね」と笑う彼の愛車は、もともと母親が乗っていたシボレー・アストロ。免許取得と同時に譲り受けたこの車は、彼にとってまさに家族の一員です。リュウジさんは「新しい車にはどうしても興味が湧かないんですよね。今だとアルファードが同じくらいのサイズ感ですけど、最近の車に乗っても、ボタンだらけで何が何やらわからないですし……」と、現代の最新モデルにはない、旧車の持つアナログな魅力と操作性を強く感じています。彼の言葉からは、単なる機能性だけでなく、車との間に築かれる深い絆が伺えます。
故郷の面影を乗せたN-BOX、そして12台の軽自動車
たっつんさんのN-BOX:思い出を刻むカスタム
車との特別な関係を築いているのは、アメ車オーナーだけではありません。「たっつん」さんは、母親の送迎用に購入したホンダN-BOXを、誰もが目を引くほどにド派手にカスタムしました。母親が亡くなった後も、彼はこの思い出深い車をカスタムし続けることで、生活に張りを持たせています。「最初はもう少しキレイめに仕上げる予定だったんですけどね。途中でボディにサビを入れはじめてから、かなり方向性が変わって」と語るように、彼のカスタムは単なる見た目の変更に留まらず、自身の感情や思い出を表現する手段となっています。
いっちーさん:愛情が溢れて「軽自動車12台」所有
女性オーナーの「いっちー」さんは、15年以上前にカスタムしたダイハツ・タントを今回のイベントに出展しました。さらに驚くべきは、彼女が改造車をなんと12台も所有しているという事実です。「やっぱり車を買い替えても、それまでの車を手放すと寂しくなるじゃないですか。それで、いつからか別の車を買っても残しておくようになり、そのままどんどん増えてしまって……」と、まるでペットを飼うように車を愛する様子が伺えます。周りからは「普通車を弄ればいいのに」と言われることも多いそうですが、「四角くて愛嬌のあるデザインが好きなので、軽ばっかり増えちゃって」と、軽自動車への特別な愛着を語ります。夫は彼女のこの趣味に対して「申し訳ない気持ちもありつつ、もうずっと、私の趣味に関しては見て見ぬフリという感じです。たまに代車とかでノーマルの車に乗ると、『こういうのでいいのになぁ』と呟いていることはありますけどね」と、半ば呆れつつも温かく見守っているようです。
車は移動手段以上の存在へ
「37th MOONEYES Street Car Nationals®」で出会った個性豊かなオーナーたちの物語は、車が単なる移動手段ではないことを強く示しています。彼らにとって車は、自己表現のキャンバスであり、人生のパートナーであり、時には思い出を繋ぐ大切な存在です。自らの手で修理し、カスタマイズし、愛情を注ぎ込むその過程こそが、彼らの生活を豊かにし、情熱を燃やす原動力となっています。たとえ「アメ車が売れないこの国」であっても、車に対する深い愛情と、それを表現する独自のカーカルチャーは、確かに日本の地に息づき、進化し続けているのです。