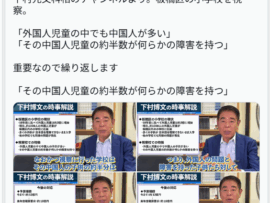近年、高齢者を狙った特殊詐欺の被害が深刻化しています。離れて暮らす親を持つ多くの人々が「自分の親もいつか被害に遭うのではないか」と不安を抱えながらも、頑固な親にどう説得し、どのような対策を講じるべきか頭を悩ませています。一度被害に遭えば、金銭的な損失だけでなく、精神的なダメージも甚大です。では、このような状況を防ぐため、私たちは一体何ができるのでしょうか。
高齢者の特殊詐欺被害、深刻化する現状
警察庁の2024年の特殊詐欺関連統計によると、全国の被害総額は700億円を超え、前年比で58%も増加という憂慮すべき状況です。これは1日当たり約2億円もの被害額に相当し、そのうち65歳以上の高齢者が占める被害は全体の65%にも上ります。
まさに「誰でも詐欺に遭う時代」であり、実家が詐欺集団の「カモリスト」に載るのも時間の問題だと感じている人も少なくないでしょう。仮名である立花武雄さん(60歳)もその一人です。彼は87歳の一人暮らしの母親の認知症の進行と寂しさにつけ込まれ、特殊詐欺の標的とならないかと懸念していました。しかし、対策を促しても母親は「心配無用」と聞き入れず、具体的な防衛策を講じられないまま、ある日突然、600万円もの大金を騙し取られてしまいます。
 高齢者を狙う特殊詐欺のイメージ。不安そうな表情の高齢者と、詐欺師を示唆する人物の手元。
高齢者を狙う特殊詐欺のイメージ。不安そうな表情の高齢者と、詐欺師を示唆する人物の手元。
詐欺被害が招く深刻な影響:家計と心の負担
立花さんの母親は、長年の勤労で退職金を含め1500万円の貯蓄がありましたが、年金だけでは生活費が不足し、毎月2万円ほど取り崩していました。結果的に貯蓄は1000万円弱まで減少し、そこから詐欺によって600万円が消えたことで、手元に残ったのは400万円あまり。この金額は、将来の老人ホーム入居一時金として確保しておきたい資金でした。
息子である立花さんは、母親に対し「だからあれほど言っただろ!」と怒りをぶつけ、もっと早く定期預金にする、あるいは家族信託や成年後見制度を利用していればと悔やみます。立花さん自身、すでに定年を迎え、再雇用で給与が半減しているため、母親の生活費を毎月数万円仕送りするのは極めて困難な状況です。
金銭的な損失に加え、母親の精神状態も深刻でした。詐欺被害後も、母親の名前と電話番号は特殊詐欺の「闇名簿」に載っているようで、似たような詐欺の電話が頻繁にかかってきます。定年後、知人からの電話がめっきり減った母親は、誰かから電話がかかってくることを喜び、たとえ立花さんが隣にいても犯人と話し込んでしまうのです。実際、警視庁の調べによると、65歳以上の女性の被害は男性の3倍にも上り、「子どもや孫を助けたい」という情につけ込まれやすく、犯罪の手口に詳しくないことがその理由とされています。
立花さんは、非通知電話には出ないこと、知らない電話番号はまずインターネットで検索して確認することを伝えましたが、母親は耳を傾けません。ついに立花さんは怒鳴って母親のスマートフォンを取り上げてしまいました。これにより通信料は削減できましたが、母親はショックでふさぎ込み、軽いうつ病のような状態に陥り、会話も外出もままならなくなってしまいました。
頑なな親への効果的なコミュニケーションと予防策
この痛ましい事例から、私たちは「親が被害に遭う前に、どう対応すべきだったのか」という重要な問いに直面します。頑なな親に対し、一方的に叱ったり、対策を押し付けたりすることは、かえって事態を悪化させる可能性があります。
親の寂しさや、社会とのつながりの希薄さが詐欺の温床となることも少なくありません。詐欺の手口を具体的に伝えるだけでなく、もしもの時に誰に相談すれば良いか、例えば「詐欺被害ホットライン」のような公的な窓口の存在を教え、一緒に調べてみるなどのアプローチも有効です。また、金融機関と連携した高齢者向けの振り込め詐欺対策サービスの利用を検討したり、家族信託や成年後見制度といった財産管理の仕組みについて、早い段階で親子で話し合っておくことも、将来のトラブルを防ぐ上で極めて重要です。
親の尊厳を尊重しつつ、寄り添いながら、段階的に対策を進めるコミュニケーションが求められます。
結論
高齢者を狙った特殊詐欺の被害は増え続け、私たち家族にとって避けては通れない社会問題となっています。金銭的な被害だけでなく、被害者の精神的な健康、そして家族関係にまで深刻な影響を及ぼします。大切な親を守るためには、統計データが示す厳しい現実を認識し、早期かつ継続的な対策が不可欠です。
頑なな親へのアプローチは簡単ではありませんが、頭ごなしに否定するのではなく、親の気持ちに寄り添い、具体的な予防策を分かりやすく、根気強く伝える努力が求められます。必要に応じて、警察や消費者センター、あるいは弁護士などの専門機関に相談することも視野に入れ、家族全体で詐欺対策に取り組むことが、何よりも重要であると言えるでしょう。
参考文献
- 警察庁 特殊詐欺関連統計