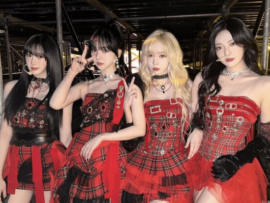新学期が始まる9月1日は、一年で最も子どもの自殺が突出して多い日とされています。学校への不安や絶望を抱え、大人に苦しみを打ち明けられない子どもたちの問題は、社会にとって喫緊の課題。精神保健福祉士の植原亮太氏の解説を基に、この背景と子どもたちの心に寄り添う本質的な方法を深掘りします。
 子どもの自殺を防ぐために寄り添う親と子どもの手。9月1日を前に、大人の心の健康も重要視されるべきだ。
子どもの自殺を防ぐために寄り添う親と子どもの手。9月1日を前に、大人の心の健康も重要視されるべきだ。
9月1日に子どもの自殺が突出する背景と「親子関係」の本質
夏休み明け、多くの学校で新学期が始まる9月1日は、文部科学省の調査によると、18歳以下の日別自殺者数が一年で最も突出して高い数値を示しています。学校が始まることへの強い不安や絶望感を抱え、その苦しみを大人に打ち明けられない子どもたちが、追い詰められてしまう現状があります。この子どもの自殺問題が議論される際、主に二つの視点が挙げられます。一つは、SNSの発展による有害情報への容易なアクセスなど、「時代性の変化」が子どもたちの心に与える影響です。しかし、人の心の奥底には時代を超えて変わることなく継承される本質的な欲求も存在します。

その本質とは「わかってもらいたい」「関心を向けてもらいたい」という、人間が生まれつき持つ根源的な気持ち、すなわち親子関係における「愛着(アタッチメント)」です。幼少期に親(養育者)に向けられるこの本能的な欲求は、J・ボウルビイの提唱する「愛着理論」に基づき、子どもが安心感を求め、親に寄り添うことで満たされます。この根深い欲求が満たされない時、子どもは深い孤独や絶望を感じやすいのです。
私たちは、この愛着という欲求にいかに忠実に生き、そしていかにその影響を受けているかを知ることが、自殺にまで追い込まれてしまう子どもの心の問題を理解する上で不可欠です。大人自身の目線で「何が問題か」を判断するのではなく、子どもが「何を伝えたいのか」「何に苦しんでいるのか」を、彼らの視点から理解しようと努めること。これこそが、子どもたちのSOSを受け止め、絶望から救い出す第一歩となります。
新学期が始まる9月1日、子どもの自殺という悲劇を防ぐには、時代性だけでなく、子が根源的に抱く「わかってもらいたい」という愛着の欲求を理解することが不可欠です。大人自身の心の健康を保ちつつ、子どもの声に耳を傾け、彼らの視点から苦しみを理解しようと努めること。これが、絶望に瀕した子どもたちを支え、未来へと導く確かな一歩となるでしょう。
参考文献:
- 文部科学省「児童生徒の自殺に関する調査」
- J・ボウルビイ「愛着理論」