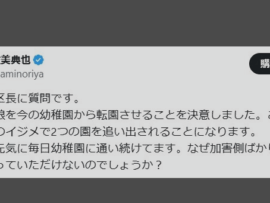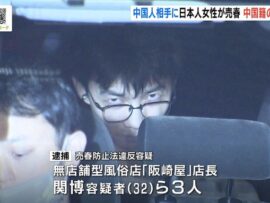現代社会において、人間関係の悩みや対人関係での疲労感は多くの人が抱える共通の課題です。「人と会うのがしんどい」「なぜか社交の場が苦痛に感じる」といった感情に囚われ、夜眠れないほど思い悩むことも少なくありません。しかし、その“苦手意識”は、もしかしたら無意識のうちに自分を縛り付けている「思い込み」かもしれません。ベストセラーシリーズを多数手掛ける精神科医Tomy氏が、著書『精神科医Tomyが教える 1秒で不安が吹き飛ぶ言葉』の原点となった考え方を基に、その真実に迫ります。社交に対するネガティブな感情の裏に隠された「良い疲れ」の可能性と、そこから抜け出すヒントを探ります。
多忙な社交の中で見出す「心地よい疲れ」
先日、神戸で開催された学会に出席した際、精神科医Tomy氏は多くの人々と交流する機会を得ました。長時間にわたる社交活動は、当然ながら疲労を伴います。しかし、Tomy氏はこの時の疲れを「心地よい疲れ」と表現しています。それは単なる肉体的な疲労ではなく、多様な人との出会いや議論から得られる刺激がもたらす、精神的な充実感を伴うものだったのです。このような経験は、社交が必ずしもネガティブな側面ばかりではないことを示唆しています。
「苦手」は「疲れやすい体質」に過ぎない?思い込みの罠
Tomy氏自身も、元来は特定の相手とだけ深く付き合うことを好むタイプで、「人付き合いが苦手」という認識を持っていたといいます。しかし、実際に多くの人と関わる場に出てみると、その場は案外楽しく過ごせることに気づかされます。問題はその後に訪れる「どっと押し寄せる疲労感」です。この疲労が引き金となり、「やはり自分は人付き合いが苦手なのだ」という思い込みを強めてしまう傾向があります。しかし、Tomy氏はこの状況を「苦手なのではなく、『人と関わると疲れやすい体質』なだけかもしれない」と指摘します。これは、自身の性質を悲観的に捉えるのではなく、客観的に理解しようとする重要な視点です。
 自宅で一人、静かに過ごすことで人付き合いへの苦手意識を深めている人物
自宅で一人、静かに過ごすことで人付き合いへの苦手意識を深めている人物
自宅の安心感が深める「人付き合いの壁」
人との交流を終え、自宅に帰って一人になったときの安心感は、たしかに絶大です。この深い安心感に慣れてしまうと、「やはり自分は人と関わらない方が楽だ」という思考が強化されます。本来、外出先で楽しい時間を過ごしていたはずなのに、そのポジティブな体験は忘れ去られ、一人でいることの快適さばかりが印象に残ってしまいます。このサイクルが、「自分は人付き合いに向いていない」という思い込みを一層強固にし、結果的に人との関わりを避けるという悪循環へと繋がってしまう危険性があるのです。
「強制外出」の習慣が心にもたらす変化
このような「思い込み」の悪循環を断ち切るために、Tomy氏が提案するのは、無理のない範囲で「外に出る習慣」を意識的に作ることです。友人からの誘いなど、スケジュールが許す限りは積極的に応じてみることを勧めています。これはまるで「強制お出かけ」のように感じるかもしれませんが、その経験が後々、自身の心の健康や新たな発見に繋がるケースは少なくありません。Tomy氏のもとを訪れる患者さんの中にも、「人付き合いが苦手だ」と訴える方は多いものの、極端に苦手なケースは意外にも少ないといいます。むしろ、本人は「できていない」と感じていても、周囲からは「十分にできている」と評価されていることも頻繁にあるのです。
脳を活性化し、幸福感を引き出す社交の力
たまに外出して人と会うことは、単なる気分転換以上の効果をもたらします。それは、脳の普段使わない部分を活性化させる感覚に近いとTomy氏は語ります。これにより、頭が「お暇」になりにくく、次に何をするべきかのアイデアやインスピレーションが湧きやすくなります。この脳の活性化は、心の健康にも良い影響を与え、ちょっとした幸福感や充実感に繋がることもあります。新しい刺激は、精神的な停滞を防ぎ、前向きな気持ちを育む助けとなるのです。
思い込みをほぐし、新たな自分を発見する
「人と会うのは少ししんどいな」と感じている方でも、無理のない範囲で、たまには意識的に人との交流の機会を持ってみることを強くお勧めします。小さな外出や短時間の交流であっても、それが自分の中に凝り固まった「人付き合いが苦手」という思い込みをゆっくりとほぐし、新たな自分を発見するきっかけとなるでしょう。社交の疲れは、決してネガティブなものばかりではありません。それは、自身の成長や脳の活性化に繋がる「良い疲れ」である可能性も秘めているのです。
参考文献
- 『精神科医Tomyが教える 1秒で不安が吹き飛ぶ言葉』(ダイヤモンド社)
本稿は『精神科医Tomyが教える 1秒で不安が吹き飛ぶ言葉』(ダイヤモンド社)の著者による特別原稿を基に構成されています。