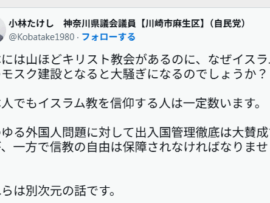私たちが日頃口にするうなぎ、特にうな重で味わうその美味しいニホンウナギは、一体どこから来ているのでしょうか。近年、ニホンウナギが絶滅危惧種のレッドリスト入りし、資源の不足が叫ばれる中、私たちが今食べているうなぎの源流を知ることは、その美味しさをより深く理解する第一歩となります。本稿では、天然うなぎと養殖うなぎのそれぞれの産地と、その変遷の歴史を紐解いていきます。
「天然うなぎ」と「養殖うなぎ」の基本知識
うなぎの供給源を理解する上で、まず知っておくべき重要な5つの点があります。第一に、うなぎには自然の川や湖で捕れる「天然うなぎ」と、養鰻場で育てられる「養殖うなぎ」が存在します。かつては天然うなぎが豊富に捕獲されていましたが、現在ではその漁獲量は激減し、私たちが消費するうなぎの実に99%が養殖うなぎであると言われています。この天然うなぎと養殖うなぎでは、その主な産地が異なる点も特筆すべきでしょう。物事の本質を捉えるためには「歴史」と「地理」の視点が不可欠であり、うなぎが天然から養殖へと変遷した経緯をたどることで、その背景がより明確になります。
 美味しそうなうな重の写真
美味しそうなうな重の写真
日本における「天然うなぎ」の産地と変化
天然うなぎの分布は、かつては青森県の小川原湖が北限とされてきましたが、2022年には北海道での天然うなぎの捕獲が確認されるという驚くべきニュースがありました。これは、地球規模の環境変化が日本の生態系、特にニホンウナギの生息域に影響を与えていることを示す、明確な事例と言えるでしょう。天然うなぎは特定の地域に偏らず、適切な環境があれば生息しうるものの、その個体数は減少の一途をたどっています。
「養殖うなぎ」主要4大産地の詳細
現在、私たちが主に食している養殖うなぎは、特定の地域に集中して生産されています。生産量の多い順に挙げると、以下の4県が日本の養殖うなぎ供給の大部分を担っています。これらの上位4県で、全国の養殖うなぎ生産量の90%以上を占めており、日本のうなぎ食文化を支える重要な拠点となっています。
- 鹿児島県: 全体の約40%
- 愛知県: 全体の約30%
- 宮崎県: 全体の約20%
- 静岡県: 全体の約10%
まとめ
私たちが味わううなぎは、そのほとんどが日本の限られた地域で大切に育てられた養殖うなぎであり、天然うなぎは稀少な存在となっています。ニホンウナギがレッドリストに記載された現状を鑑みると、その産地や変遷の歴史を知ることは、単なる食の知識に留まらず、持続可能な資源利用や環境問題への意識を高める上でも重要です。これからも、うなぎの美味しさを楽しみながら、その背景にある歴史と現状にも目を向けていきたいものです。
参考文献
- 高城 久 著, 『読めばもっとおいしくなる うなぎ大全』, 講談社, (一部抜粋・編集)