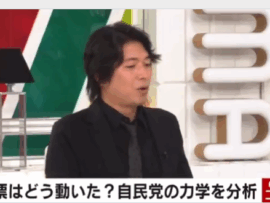近年、日本の教育現場では、教員の過酷な労働環境が深刻な問題として浮上しています。長時間労働が常態化し、過労死ラインを大幅に超える勤務を強いられるだけでなく、校内いじめや、いわゆる「モンスターペアレント」への対応など、精神的な負担も大きい業務が教員たちを追い詰めています。その結果、うつ病をはじめとする精神疾患で休職を余儀なくされたり、最悪の場合、過労死に至る悲劇が頻繁に報じられるようになりました。
横浜市の公立中学校で保健体育の教員を務めていた工藤義男さん(享年40)も、その犠牲者の一人です。遺族の計算によれば、工藤さんは亡くなる前には月間最大144時間もの時間外労働を行っていたとされています。本稿では、工藤さんの事例を通じて、教員の労働問題の現状と、真に意味のある「教員の働き方改革」を実現するための課題について深く考察します。
公務災害認定の厳しい現実
教員の過重労働による健康被害や死亡が「公務災害」として認定されるには、非常に高いハードルが存在します。たとえ校長がその事実を認め、申請に合意したとしても、公務員である教員の公務災害認定プロセスは、民間企業の労災申請と比較して、遺族側に膨大な資料提出を求めるという点で極めて困難を極めます。
特に過労死の場合、亡くなる前の6ヶ月間の勤務状況が、その死因が仕事に起因するか否かを判断する際の重要な要素となります。民間企業の労災申請では、原則として申請書を提出すれば監督官による調査が始まりますが、公務災害の場合は、申請の前提として最初から大量の詳細な資料提出が求められるのです。
具体的な例として、工藤義男さんの遺族は、彼が亡くなる前6ヶ月間の毎日の詳細なスケジュールを提出するよう求められました。起床時間、出勤時間、個々の業務内容(業務A、業務B、部活動など)、帰宅時間、就寝時間に至るまで、極めて詳細な記録をフォーマットに記入するよう指示されたのです。これは、数ヶ月前の自身の生活ですら正確に記憶している人が少ない中で、遺族が故人の勤務状況を詳細に把握し、記入することは、無理難題以外の何物でもありません。遺族が勤務先の状況を把握しているわけではないにもかかわらず、その詳細を求められることは、申請者にとって計り知れない時間的、精神的負担となります。
 多忙な教員のイメージ
多忙な教員のイメージ
幸いにも、工藤さんの元同僚の教員たちが協力してくれたことで、亡くなる前の勤務実態を示す予定表などの資料を入手することができました。これにより、遺族は「学校からもらった記録や自身の手帳などを突き合わせてなんとか書いたが、時間的にも、精神的にも負担が大きかった」と語っています。もし元同僚たちの協力が得られなかったならば、これらの書類を作成することすら不可能であった可能性が高いのです。
「教員の働き方改革」への課題と展望
工藤義男さんの事例が示すように、教員の過重労働問題は単なる長時間労働に留まらず、その後の公務災害認定プロセスにおいても遺族に多大な苦痛と負担を強いるという、二重の課題を抱えています。現在の公務災害認定制度は、遺族が故人の勤務実態を詳細に証明することを過度に要求しており、これは精神的にも肉体的にも疲弊している遺族にとって、極めて厳しい現実を突きつけています。
過労死した教員、工藤義男さんの家族写真イメージ
真の意味での「教員の働き方改革」を実現するためには、単に労働時間を短縮するだけでなく、教員個人の負担軽減、精神的サポートの充実、そして万が一の際に遺族が適切な補償を受けられるよう、公務災害認定制度の抜本的な見直しが不可欠です。教員が安心して職務に専念できる環境を整備し、その健康と命を守ることは、日本の教育の未来を支える上で最も重要な課題の一つと言えるでしょう。
参考資料
- 〈広島・京都の修学旅行の引率から帰宅→心肺停止に…「精神的にも肉体的にも強い人」だった男性教師(40)に同僚が発した「驚きの一言」〉 から続く
- Source: https://news.yahoo.co.jp/articles/4b9cfc5b705f38a6ce7acae6793a60138f8b13ab