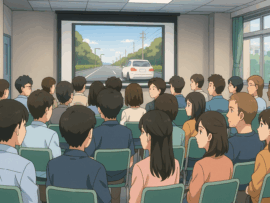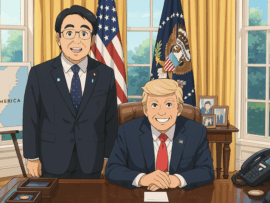原爆投下から80年を迎えた広島市で8月6日に執り行われた平和記念式典は、例年とは異なる形で世界の注目を集めました。主催する広島市は、今年の式典における各国代表の参列要請方法を、これまでの「招待」から、日本と外交関係のある国・地域への開催「通知」形式へと変更。この異例の措置は、特定の国を選別することへの批判を避けるための「苦肉の策」とされましたが、結果的に過去最多となる計120の国・地域と欧州連合(EU)代表部が出席する異例の事態となりました。
広島市が「通知」形式へ転換した背景
広島市が参列要請の形式を見直した背景には、近年の国際情勢の複雑化と、それに伴う批判がありました。ウクライナ侵攻が始まった2022年から昨年まで、広島市はロシアとその同盟国であるベラルーシへの招待を見送っていました。その一方で、昨年パレスチナ自治区ガザを攻撃するイスラエルを招待したことで、市民などから「二重基準」であるとの強い批判に直面しました。これに対し、長崎市は昨年の式典でイスラエルを招待せず、米国や英国などの大使が欠席する事態に発展するなど、平和式典のあり方が国際政治に翻弄される現実が浮き彫りになっていました。こうした状況を受け、広島市は外務省などと協議を重ね、参列要請の方法を根本的に見直すに至ったのです。
過去最多の参加国と各国の複雑な反応
新たな「通知」形式への変更は、当初、参加国数の減少を招く懸念も指摘されていましたが、結果的には過去最多の国・地域の代表が出席するという想定外の成果をもたらしました。これは、広島市が目指す平和へのメッセージが広く受け入れられた証とも言えます。しかし、その中では各国の複雑な思惑と反応が交錯しました。
台湾の初参列とパレスチナの不満
今回の式典で特に注目されたのは、初めて参列を果たした台湾の動向です。式典後に記者会見を行った台北経済文化代表処の李逸洋代表(大使に相当)は、「台湾がいかに平和を重視しているかを国際社会に意思表明することができる」と述べ、広島市の対応を高く評価し歓迎の意を表明しました。これは、台湾が国際舞台での存在感を高め、平和への貢献をアピールする機会となりました。
一方、パレスチナのシアム駐日大使は、イスラエル代表の同席に対し、式典前日の5日に強い不満を表明しました。大使は「犯罪者と被害者を一緒に招くのは不公平だ」と訴え、ガザ地区での紛争を背景にした現在の複雑な政治状況を反映する発言となりました。
 広島平和記念式典に初参列し、記者会見する台北経済文化代表処の李逸洋代表
広島平和記念式典に初参列し、記者会見する台北経済文化代表処の李逸洋代表
ロシアの欠席と批判の表明
一転して市から通知を受け取ったロシアは、今年も式典を欠席しました。ロシアのノズドレフ駐日大使は6月、ロシアの政府系メディアの取材に対し、「市指導部が政治的な姿勢を改めず、(これまでの対応に)形式的な謝罪すらない」と述べ、広島市の対応を改めて批判しました。ロシアの欠席は、ウクライナ侵攻を巡る国際的な対立が、平和記念式典という場にも影を落としている現状を示しています。中国もまた、今年も式典への出席を見送りました。
広島市が目指す平和へのメッセージ
広島市の担当者は、今回の対応について取材に対し、平和記念式典はあくまで核兵器廃絶と恒久平和の実現を広く世界に呼び掛ける場であると強調しました。国際政治の駆け引きに翻弄されることへの懸念を示しつつも、「見直しが広く受け入れられた」として、新たな形式が成功したことに安堵の表情を見せました。
今回の広島平和記念式典は、国際的な紛争や対立が深まる中でも、平和への願いを共有し、対話の場を提供することの重要性を改めて浮き彫りにしました。形式の変更が、より多くの国・地域の参加を促し、平和へのメッセージを強化する一助となったことは、今後の国際社会における平和活動のあり方を考える上で重要な示唆を与えています。