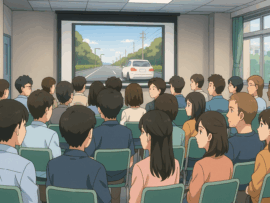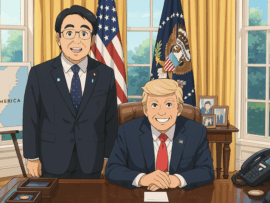なぜ大日本帝国はアメリカとの戦争に踏み切り、そして敗北したのか。連合艦隊司令長官の山本五十六が「アメリカと戦争したら負ける」と考えていたにもかかわらず、ある理由から真珠湾攻撃を強行に推進したとされるこの歴史的転換点について、日本海軍史研究者であり大和ミュージアム館長の戸高一成氏の分析をもとに、その複雑な背景を深掘りします。
 日本海軍の対米戦決断に至る複雑な背景と山本五十六の懸念を象徴するイメージ
日本海軍の対米戦決断に至る複雑な背景と山本五十六の懸念を象徴するイメージ
明治期からの「仮想敵国」としての米国
日本が「アメリカとの戦争」を初めて意識したのは、日露戦争後の明治40年(1907年)に策定された「帝国国防方針」に遡ります。この方針において、日本はアメリカを「仮想敵」として設定しました。そして、アメリカとの戦いを想定した場合、その中心を担うのは海軍であるとされました。
しかし、ここで誤解してはなりません。「アメリカ=敵」ではなく、あくまで「仮想」敵であったという点です。仮想敵国を設定する目的は、それに対する防衛力を検討し、国防の方針を立て、予算編成の基準とすることにありました。極端に言えば、予算獲得のために仮想敵が必要であったとも言えます。
したがって、当初の海軍における対米意識は、アメリカ海軍を「必ず戦う相手」とは位置づけていませんでした。ところが、仮想敵としての設定が続くにつれ、海軍兵学校では「いずれ日本はアメリカと戦う」という前提で教育がなされるようになり、大正時代の中頃には「お前たちは太平洋でアメリカと戦う」という、より直接的な表現へと変質していきました。海軍兵学校50期(大正11年・1922年卒)前後の士官たちは皆、「俺たちはいずれ太平洋でアメリカと戦う」と思い込んでいたとされています。この「仮想敵」という設定が、日米衝突の根源へと変質してしまったとも言えますが、海軍内部で「本当にアメリカとぶつかるかもしれない」という意識が強まったのは、昭和15年(1940年)に締結された日独伊三国同盟の前後からです。
三国同盟を契機に高まる「対米衝突不可避」の意識
それまで「日米衝突」は「いつか」起こるものであり、今日明日の差し迫った問題ではありませんでした。しかし、三国同盟成立の前後から、「ドイツと同盟を組み枢軸側に加われば、イギリス、アメリカとの衝突は必至だ」と認識されるようになり、「対米衝突は不可避である」という意識が飛躍的に高まっていきます。
この段階で、軍令部と海軍省の横断的な組織である「海軍国防政策委員会・第一委員会」が設立され、これを中心に対米戦の準備が進められることになります。軍という組織は「抑止力機能」を持つため、大勢としては戦争回避こそが任務であり、基本的に「戦争はすべきでない」というのが常識でした。そのため、本当に「対米戦争をしなければならない」と考えて動いたのは、第一委員会などの一部の人間で、海軍全体では多数派ではありませんでした。
それでも、「アメリカとの衝突はやむを得ない」という認識のもと、事実上、対米戦争の準備が開始され、昭和15年の暮れには海軍が「出師(すいし)準備」の作業に着手しました。陸軍の「動員」とは異なり、海軍の「出師準備」は軍艦に手を加える大がかりな作業です。例えば、戦艦や巡洋艦のバルジ(船体外側の膨らみ)に水密パイプをぎっしり詰めて不沈対策を行うと、その部分は人間が入ることができず、メンテナンスが不可能になります。その結果、通常10年保つ軍艦が5、6年で使い物にならなくなる可能性も生じます。元に戻すのも大工事であり、海軍の出師準備は一度始めると、後戻りのできない、不可逆的な作業だったのです。
このときの軍令部作戦課長だった富岡定俊が、戦後「出師準備は戦争を決意しなければ発動できない」と語っていることからも、この準備に着手したことは、海軍が戦争を決意したと見なされてもよいでしょう。少なくともその時点で、海軍が「対米戦がここ1、2年のうちに起こるのは避けがたい」と認識していたことは明らかです。
日露戦争の「再現」を狙った戦略構想
昭和15年の暮れから翌年の正月にかけて、海軍の国防と用兵を担う軍令部は、対米戦の具体的な準備を進めました。では、アメリカを相手に、どのように戦おうとしていたのでしょうか。その基本的な戦略は、明治時代の帝国国防方針の延長線上にありました。
日本はまず、南方資源を確保するため、当然ながらアメリカの植民地であるフィリピンを攻略します。これに対して、アメリカはフィリピンを奪還し、その後北上して日本本土に向かってくる。このアメリカ艦隊を、日本はマリアナ諸島ないしは小笠原諸島のラインで邀撃(ようげき=迎撃)し、決戦を挑む――。要するに、日本海軍にとって最も輝かしい歴史である、日露戦争における日本海海戦の成功体験の再現を狙っていたのです。
結論
日本海軍が、当初は防衛予算確保のための「仮想敵」に過ぎなかったアメリカを、やがて「必ず衝突する相手」と認識し、ついには避けられない戦争へと突き進んでいった経緯は、外部環境の変化と内部論理の変質が複雑に絡み合った結果でした。特に日独伊三国同盟の締結が、それまで漠然とした「いつか」の衝突を「差し迫った不可避の現実」へと変え、後戻りできない「出師準備」へと海軍を駆り立てました。そして、その戦略は、過去の栄光たる日露戦争の再現という、ある種の成功体験への固執が見られたのです。山本五十六司令長官の予見にもかかわらず、対米開戦が不可避とされた背景には、このような海軍内部の意識変革と戦略構想が存在していました。
参考文献
- 戸高一成『日本海軍 失敗の本質』(PHP新書)
- Yahoo!ニュース: https://news.yahoo.co.jp/articles/f87617da9df71520c597a35aa3ef2ce674469299