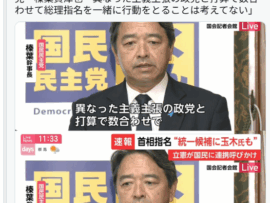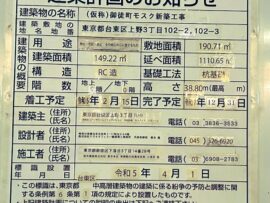戦後80年となるこの夏、第二次世界大戦の真実を改めて問い直す時が来ています。歴史の深淵には、従軍戦争特派員たちが命がけで記録した貴重な写真が残されています。これらの写真、特に「不許可」とされたものが、当時の情報統制と隠蔽の現実を鮮明に浮き彫りにします。本稿では、写真が語る知られざる戦場の実像と、戦時下の日本における情報統制の仕組み、そしてそれらが戦後80年の私たちに何を伝えるのかを深掘りします。
 上海戦線羅店での日本軍突撃の様子を捉えた写真。戦争特派員が見た日本軍の現実を示す貴重な記録。
上海戦線羅店での日本軍突撃の様子を捉えた写真。戦争特派員が見た日本軍の現実を示す貴重な記録。
戦争特派員たちが記録した「知られざる現実」
戦後80年が経過した現在、私たちは戦争の姿をどこまで正確に把握できているでしょうか。残念ながら、日本各地の新聞社や通信社は、物資の不足、軍による廃棄命令、激しい空襲、そしてGHQによる接収といった様々な要因により、戦時中に撮影した多くの写真を残すことができませんでした。例えば、毎日新聞東京本社(旧・東京日日)でさえ、「終戦」の際に所蔵していた大量の写真を焼却せざるを得ませんでした。
しかし、毎日新聞大阪本社(旧・大阪毎日、通称「大毎」)が秘蔵してきた「毎日戦中写真」の中には、奇跡的にも、戦火の中で軍と行動を共にした戦争特派員自身の姿を捉えた約400点もの貴重な写真が残されています。これらの写真は、軍人の視点とは異なる「もうひとりの人間」、すなわち報道の最前線にいた特派員たちの目を通して、戦争の実情や彼らの過酷な任務を生き抜いた様子を伝えてくれる貴重な手がかりとなります。
「不許可」写真に秘められた真実と検閲の実態
「毎日戦中写真」には、「不許可」と判断された写真が少なからず含まれています。これらは、社内外の厳格な検閲によって、大毎・東日が報道できなかったり、しなかったりした写真です。「不許可」とされた写真や、そもそも撮影すら許されなかった写真の背後に隠蔽された事実を精査し、視覚的記録から抹消された情報を再構築することは、戦争の全体像を理解する上で極めて重要です。
当時の報道機関では、海外に派遣された特派員たちが撮影したオリジナルネガは、連絡船や空輸によって大阪本社に運ばれ、厳重に保管されていました。一般的には、これらのネガは大毎写真部で現像・焼き増しされ、大阪、東京、西部、中部の各編集局に1枚ずつ、さらに陸軍省、海軍省、内務省、内閣情報部にそれぞれ1枚ずつが、列車便などで送付されました。毎日戦中写真の資料を見る限り、憲兵隊や特別高等警察(特高)による直接的な検閲の痕跡はほとんど見当たりません。
ただし、日本本土に向けて写真が送られる以前に、すでに海外の現地機関で事前検閲が行われていた点には注意が必要です。明治期から、国内・海外を問わず、各地の要塞司令部が写真や絵葉書などを検閲していたことは、よく知られた事実です。
多様化する検閲機関と「保留」の運用
1930年代以降、戦時色が強まるにつれて検閲機関はさらに多様化していきました。支那派遣軍、関東軍、台湾軍、南方軍など、軍部による検閲が大幅に強化されたのです。
新聞社内では、送られてきたネガは密着写真や焼付写真に現像され、写真台帳に貼り付けて整理されていました。この写真台帳には、写真部が受理した日付を示す青い印や、撮影月日、場所、撮影者などのメモが手書きで残されています。
とりわけ重要なのは、東京本社からの連絡に基づき、写真の使用が許可されない場合には「不許可」の赤い印が、許可された場合には「陸軍省検閲済」「海軍省許可済」「情報局検閲済」といった赤い印が、社内での整理の過程で押されていたことです。その他、「保留」などの印が押され、許可が出るまで一時的に使用が禁止されるケースもありました。
結び
戦争特派員たちが残した写真、特に「不許可」とされたものは、戦時下の日本における徹底した情報統制と隠蔽の現実を浮き彫りにする貴重な歴史的証拠です。これらの視覚的記録は、表には出なかった真実を私たちに伝え、戦後80年を迎える今、戦争の多角的な姿を理解し、その教訓を未来へ繋ぐための重要な手がかりとなります。彼らの残したレンズ越しの視線は、現代を生きる私たちに、歴史を深く探求することの重要性を改めて問いかけているのです。
参考文献
- 貴志俊彦『戦争特派員は見た 知られざる日本軍の現実』(講談社現代新書)