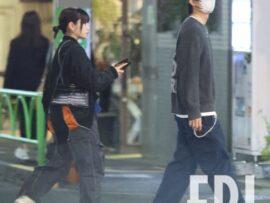第二次世界大戦末期の1945年8月、ソ連軍が満州へ侵攻した際、多くの民間人が悲劇に見舞われました。中でも、西部国境に近い地域で起きた「葛根廟(かっこんびょう)事件」は、ソ連軍による民間人殺害事件として最大規模の一つとされています。この事件では、日本人避難民1000人以上が無差別な攻撃の犠牲となりました。現場の草原には女性や子どもの悲鳴が響き渡り、血の海に倒れた母親にすがりつく赤ん坊の姿もあったと言われています。本記事では、この満州の地で繰り広げられた想像を絶する惨劇の全貌を、生存者の証言や当時の状況に基づき深く掘り下げます。
満州の民間人を襲ったソ連軍の侵攻:葛根廟事件の勃発
1945年8月、ポツダム宣言受諾を目前に控えた日本に対し、ソ連は一方的に宣戦布告し、満州国へと侵攻を開始しました。関東軍の一部は既に転属していたため、ソ連軍の前面に立たされたのは、武装が不十分な国境守備隊や、各地に居留していた民間邦人、開拓団員らでした。彼らは突然の侵攻に巻き込まれ、故郷を離れて異国の地で暮らしていた家族は、極度の混乱と恐怖に陥りました。
[ 満州「葛根廟事件」で、ソ連軍戦車と機関銃による民間人への無差別攻撃の様子。避難民が虐殺された悲劇的な瞬間を示す(©早田貫一、平和祈念展示資料館提供)]
満州「葛根廟事件」で、ソ連軍戦車と機関銃による民間人への無差別攻撃の様子。避難民が虐殺された悲劇的な瞬間を示す(©早田貫一、平和祈念展示資料館提供)]
「葛根廟事件」は、終戦前日の8月14日、満州国の西部国境に近い葛根廟付近で発生しました。約1300人もの女性や子どもが大部分を占める避難民の列に、ソ連軍の戦車14両を含む部隊が追いついたのです。当時9歳だった大島満吉氏(取材当時85歳、東京都練馬区在住)は、この惨劇の生存者の一人です。
大島氏の証言によると、休憩中に「戦車だ、逃げろ」という声が上がり、人々は一斉に走り出しました。エンジンの轟音とともに丘の稜線から現れたソ連軍の戦車は、無抵抗の避難民に向けて機関銃の掃射を始めました。戦車はうなりを上げてジグザグ走行し、立ちすくむ人、逃げ惑う人を次々とキャタピラでひき潰していきました。耳を劈くキャタピラの音、エンジンのきしみ、そして逃げ惑う人々の悲鳴が混じり合い、地獄絵図のような光景が繰り広げられました。機関銃の猛烈な掃射音とともに、人間の体が空中に跳ね上がるのが見えたと大島氏は語ります。
大島氏は母親とともに近くの溝に身を潜めました。一度はソ連兵と視線が合ったものの、彼らは銃を自分たちに向けず、別の方向を掃射しながら遠ざかっていきました。必死にうずくまるうち、銃声は徐々に遠のいていきました。溝から這い上がると、そこには何百もの死体が折り重なっていました。そして夜になり、生き残った人々の中には、絶望のあまり自決を選ぶ者も現れたといいます。
葛根廟事件は、第二次世界大戦末期におけるソ連軍による残虐行為の中でも、特に記憶されるべき民間人虐殺事件の一つです。多くの日本人避難民が、無防備な状況で生命を奪われたこの悲劇は、戦争がもたらす極限の惨禍と、民間人の脆弱性を改めて浮き彫りにしています。歴史の教訓として、二度とこのような悲劇が繰り返されないよう、その記憶を継承していくことの重要性が強く認識されます。
参考文献
- 永井靖二 著, 『満州スパイ戦秘史』, 朝日新聞出版