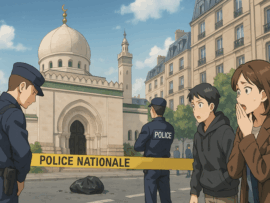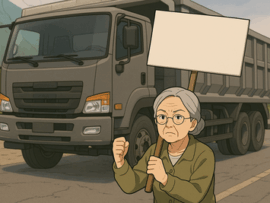日本の天皇と戦争の関わり、そしてその存在意義、さらに今後の皇室のあり方について、昭和50年代生まれの気鋭の論者四名が徹底的な討論を展開しました。本稿では、彼らが日本の「歴史認識」、特に戦後の東京裁判史観が現代に与える影響をいかに深く掘り下げ、再考を促しているのかを詳述します。
 議論する辻田真佐憲氏、浜崎洋介氏、與那覇潤氏、先崎彰容氏の四識者
議論する辻田真佐憲氏、浜崎洋介氏、與那覇潤氏、先崎彰容氏の四識者
天皇の歴史的重みと東京裁判の意義
論者の一人である先崎彰容氏は、天皇の存在が持つ計り知れない歴史的重みを強調します。昭和天皇が終戦一周年を前にした茶話会で、663年の白村江の戦いを引き合いに出して敗戦を語った逸話を挙げ、1300年以上にわたる長大な歴史感覚を持つ存在と現代人の「責任」概念との隔たりを指摘しました。天皇の感じる「歴史の重み」は、現代のわれわれが測れるような概念ではないと述べ、その特殊性を浮き彫りにしています。
これに対し、辻田真佐憲氏は、昭和天皇の人間宣言にまつわる興味深い事実を補足します。天皇は自らの神格を否定しつつも、神の子孫である「神裔」としての側面は否定しなかったという説に触れ、これが今日まで天皇が国民のために祈る「宮中祭祀」を続けている背景にあると解説します。
與那覇潤氏は、昭和天皇が対外的な法的責任から除外されたのは、良くも悪くも東京裁判の「成果」であったと簡潔に述べ、その後の日本の歴史認識に大きな影響を与えたことを示唆します。
東京裁判史観の「手打ち」としての側面と影響
辻田氏は、東京裁判を乱暴な言い方をすれば、一種の「手打ち」や「セレモニー」であったと分析します。そこには絶対的な正義だけでなく、互いに納得できない部分を抱えながらも、一旦の決着を図ろうとする側面があったと説明します。しかし、より重要な点は、この「手打ち」であるはずの東京裁判が、戦後の日本人自身の歴史観を大きく規定してしまったことにあると指摘。具体的には、1928年の張作霖爆殺事件から敗戦までを訴追対象としたその時間軸の切り取り方が、現代においても「戦争」を考える際の一般的な枠組みとして踏襲されている現状を問題視します。
「共同謀議」論への疑問と新たな歴史認識の必要性
浜崎洋介氏は、東京裁判で問われた「共同謀議」の概念に疑問を呈します。戦争期間中に15人もの首相が交代した日本政府において、「共同謀議」のような一貫した計画が成り立つのかと問いかけます。敗戦直後は対外的な「セレモニー」としてこれを受け入れるしかなかったとしても、これを日本人自身の歴史観として固定する必要は全くない、と新たな歴史認識の必要性を強く訴えます。
與那覇氏も浜崎氏の意見に同意し、「共同謀議」論は偶発的な出来事の連鎖の背後に、一貫した邪悪な「意図」があったと想定している点で、今日の「陰謀史観」に近いと鋭く指摘。この見方が、複雑な歴史的背景を単純化し、本質的な理解を妨げている可能性を示唆します。
結論
今回の識者による対論は、昭和天皇の歴史的立ち位置、東京裁判が戦後の日本の歴史認識に与えた影響、そして「共同謀議」のような概念が孕む問題点を深く掘り下げました。彼らの議論は、単なる過去の出来事の分析に留まらず、現代に生きる私たちが日本の歴史、特に戦争と皇室の関わりをどのように捉え、再考すべきかという重要な問いを投げかけています。東京裁判史観を相対化し、より多角的かつ nuanced な視点から歴史を理解することの重要性が浮き彫りになりました。
参考文献
- 文藝春秋