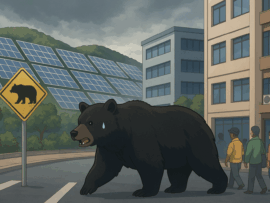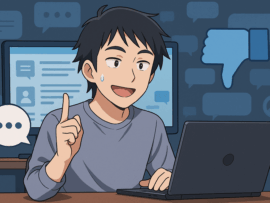皇位継承の重要性を担う悠仁親王の「成年式」が、間もなく執り行われることで大きな注目を集めています。これは、男性皇族としては実に40年ぶりとなる歴史的な儀式であり、皇室における「成年の証し」とは何か、その伝統と現代における意味合いが改めて問われています。宗教学者の島田裕巳氏によると、衣服や冠を改めることは、皇族にとって極めて重要な通過儀礼であり、男性皇族の儀式の中心には「加冠の儀」があります。一方、女性皇族の成年ではティアラの着用がその象徴となりますが、愛子内親王の場合はコロナ禍の影響で新調が見送られた経緯もあります。本稿では、悠仁親王の成年式を中心に、皇室の成年儀礼の歴史と現在の姿を深く掘り下げていきます。
 新年一般参賀にご臨席の愛子内親王殿下と皇室の方々
新年一般参賀にご臨席の愛子内親王殿下と皇室の方々
悠仁親王「成年式」の全容:40年ぶりの男性皇族の儀式
悠仁親王殿下が19歳を迎えられる2025年9月6日に、「成年式」が執り行われる予定です。この成年式は、秋篠宮殿下以来40年ぶりの男性皇族の成人を祝う儀式となるため、国民の大きな関心を集めています。式典後には、8日に三重県の伊勢神宮と奈良県の神武天皇陵へ、9日には東京の八王子市にある昭和天皇陵へ、それぞれ参拝される予定です。
伝統的な「加冠の儀」:成年の証しとしての冠
成年式当日の朝、悠仁親王殿下は、天皇陛下のお使いから成年用の冠をお受け取りになります。午前中には皇居の宮殿にご古式ゆかしい装束姿で臨まれ、未成年用の冠から成年用の冠に付け替える「加冠(かかん)の儀」が執り行われます。この儀式は、古来の「元服」に通じるものであり、衣服や冠を改めることが成年に達したことの確かな証しとされてきました。その後、儀式用の馬車で移動され、皇居内の宮中三殿を参拝されます。
「朝見の儀」と最高位勲章の授与
午後の成年式では、悠仁親王殿下は燕尾服にお召し替えになり、天皇皇后両陛下にご挨拶される「朝見(ちょうけん)の儀」に臨まれます。この儀式の中で、天皇陛下から直接「大勲位菊花大綬章(だいくんいきっかだいじゅしょう)」が授与されます。この勲章は日本における最高位の勲章であり、戦後は親王殿下に授与されるほか、歴代の首相経験者にはその没後に授与されてきたものです。
私的な夕食会と小室夫妻の動向
成年式の夜には、秋篠宮ご夫妻が主催される私的な夕食会が都内の民間施設で開催されます。この夕食会には、皇族方や元皇族の方々が招かれる予定です。かねてから注目が集まっていた、アメリカに滞在中の小室圭さん・眞子さんご夫妻が参列するかどうかについては、今回は見送られる見通しとされています。
女性皇族の成年の証し:変化する伝統とティアラの役割
男性皇族の成年式が「加冠の儀」を中心とする一方で、女性皇族の成年儀礼は時代とともにその姿を変えてきました。
「裳着」から洋装へ:伝統的な成年の儀式の変遷
かつて女性皇族の元服にあたる儀式は「裳着(もぎ)」と呼ばれていました。裳とは十二単の一部で、後方に長く引きずるスカート状のものを指し、裳着ではそれを初めて身に着けました。裳着の前には、それまで垂らしていた髪を結い上げ、成人女性の髪型に改める「髪上げ」が行われ、時代によっては「お歯黒」や「引眉(ひきまゆ)」も伴いました。これらの儀式は12歳から14歳くらいに行われ、結婚の準備が整ったことを示すものでした。
しかし、明治時代になると、政府は欧米の近代国家にならい、宮中の儀式における皇族の装束を洋式に改めました。これにより、十二単に代表される和装の儀式は廃れ、「ローブ・デコルテ」と呼ばれる西洋風のロングドレスが女性皇族の正装として定着。これに伴い、「裳着」の儀式は行われなくなりました。
「ティアラ」と勲章:近代における成年の象徴
「裳着」に代わる新たな成年の証しとして導入されたのが、勲章と「ティアラ」でした。これも欧州の王室文化に倣ったもので、勲章としては「宝冠大綬章(ほうかんだいじゅしょう)」が授与されるようになりました。ティアラは、女性皇族が成人し、公的な場にふさわしい装いを整える象徴として、その役割を担っています。愛子内親王殿下の場合、コロナ禍によりティアラの新調が見送られ、天皇陛下の妹である清子さんのティアラを借りて公務に臨まれたことも、記憶に新しいでしょう。
伝統を継承し、未来へ向かう皇室の成年式
悠仁親王の成年式は、皇室の伝統が現代に受け継がれる重要な節目となります。男性皇族にとっての「加冠の儀」や女性皇族の「ティアラ」は、単なる装飾品ではなく、それぞれが皇族としての成長と公的な役割を自覚する「成年の証し」であり、極めて象徴的な意味を持っています。時代とともに儀式の形式は変化しても、その根底にある「通過儀礼」としての精神は脈々と受け継がれており、悠仁親王殿下が今後、皇位継承者としてその重責を担われる上での第一歩となるでしょう。この成年式は、皇室が伝統を守りつつも、時代の変化に適応しながら未来へと歩みを進める姿を私たちに示しています。