近年、社会問題としてその深刻さを増している「毒親問題」。子どもを思い通りに支配しようとする過干渉、暴言、暴力は、子どもたちに将来にわたる深い生きづらさを与えています。1990年代後半から被害が顕在化し始め、今ではその実態が広く認識されるようになりました。最近では、女優の遠野なぎこ氏が実母からの虐待経験を公にしていたことが記憶に新しいでしょう。これまでの毒親に関する議論では、特に母と娘の関係がクローズアップされがちでしたが、現実には、母親が息子を精神的に追い詰め、その人生を破壊してしまうケースも少なくありません。ノンフィクション・ライターの黒川祥子氏は、そうした「毒母」に人生を翻弄された息子たちへの連続インタビューを通じ、彼らの過酷な半生を丹念に追っています。この連載の第一回では、幼少期から塾経営者の母親に難関大学への進学を強く押し付けられ、その「期待」に応えながらも、結果的に長期間の「ひきこもり」として人生を過ごすことを余儀なくされている60代男性の物語が語られます。
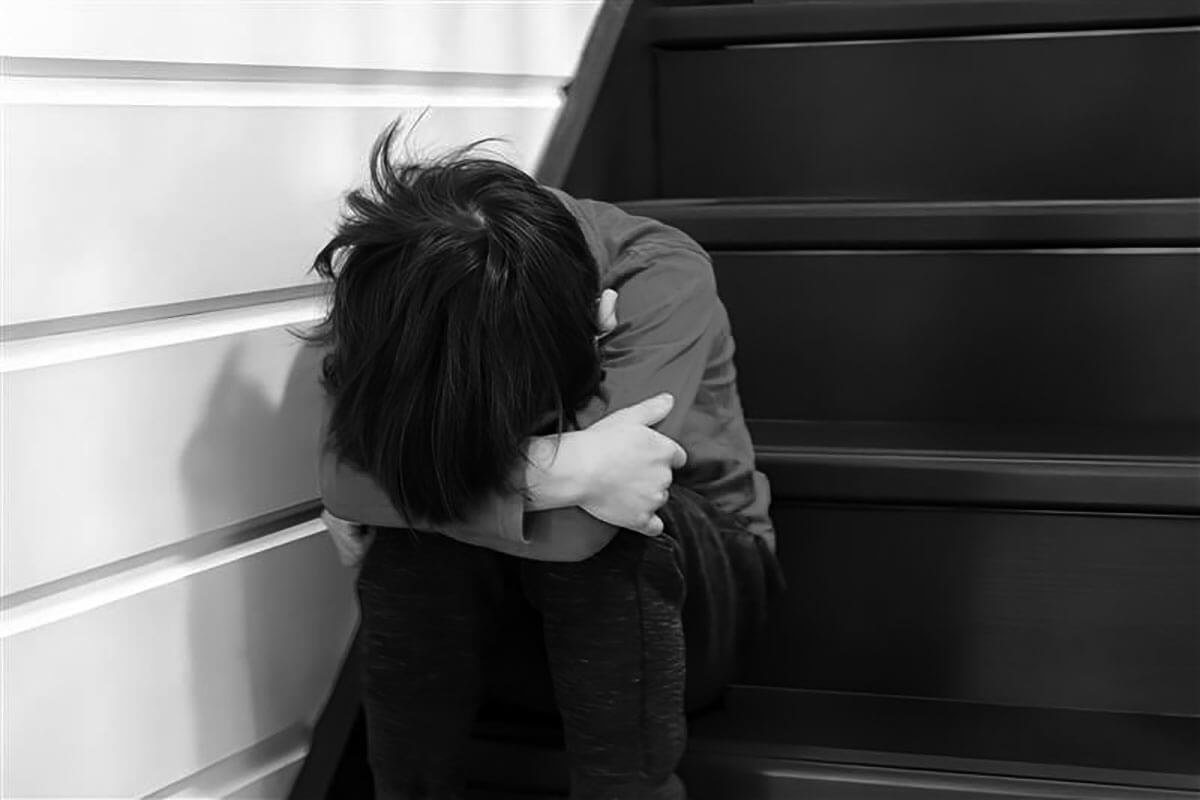 毒親による深刻な親子間支配と虐待のイメージ
毒親による深刻な親子間支配と虐待のイメージ
長期化する「ひきこもり」の現実:高齢化と支援の場
ある土曜の昼下がり、公民館の和室には穏やかな静けさが満ちていました。三々五々集まってきた参加者たちがテーブルを囲み、座布団に座ります。そこは、「ひ」きこもりと、「老」いを考える、「ひ老会」と呼ばれる貴重な集いの場でした。この「ひ老会」は、ひきこもりが長期化している中高年の当事者にとって、数少ない交流の機会を提供しています。参加者のために急須で日本茶を淹れているのは、この会の主催者であり、自身も中高年ひきこもり当事者であるぼそっと池井多さん(63歳)です。中肉中背で、その穏やかな立ち居振る舞いからは人柄の良さがうかがえます。頭髪には白髪が混じり、これまでの年月を物語っていました。
「ひ老会」が提供する“安全な対話の場”
会の冒頭、池井多さんは静かな口調で会の基本ルールを伝えます。それは「言いっぱなし、聞きっぱなし」であり、批判はしないこと。そして、それぞれが「人生の当事者」として、自身の悩みや思いを語り合うことの重要性です。「皆さん、たとえひきこもり支援者である方でも、当事者として参加していただきます。誰もが皆、『人生の当事者』であるからです。全員が『当事者』という、同じ地平に立って言葉を交わすのがこの会です」彼の知性を感じさせる淡々とした語り口と、参加者への優しい眼差しからは、この場が安心して思いを分かち合える場所であることが明確に伝わってきます。車座になった一人ひとりが自己を吐露していく中で、参加者たちは互いに共感と理解を深めていきます。「『ひ老会』は、自分の中にある“答え”へと安心して降りていき、たどりつける時間と空間です」この安全な分かち合いの時間と空間こそが、ぼそっと池井多さんがこの会で最も目指しているものなのです。
毒親問題、特に毒母による息子への影響は、これまで見過ごされがちでしたが、その深い傷跡がひきこもりという形で表面化している現状は、社会全体で向き合うべき課題です。ひきこもり当事者の高齢化が進む中で、「ひ老会」のような場は、彼らが自身の経験を語り、共感を得て、内なる答えを見つけるための重要な役割を担っています。黒川祥子氏の連載は、こうした見えにくい苦しみに光を当て、毒親問題の複雑な側面と、ひきこもり支援の必要性を改めて浮き彫りにすることでしょう。
Source: https://news.yahoo.co.jp/articles/2f6fd08dd4207904dfff03f1ebf489ee1bea8d39






