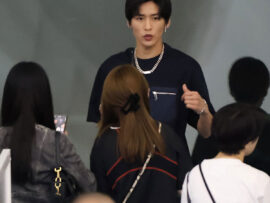ロシアとウクライナ間の紛争が続く中、「いつ戦争が終わるのか」という問いに対する明確な答えは見えず、情報過多の時代において信頼できる情報源を見極めることが一層重要となっています。東京大学先端科学技術研究センター准教授の小泉悠氏と軍事ジャーナリストの黒井文太郎氏の対談から、国際情勢に関するニュースやレポートの信頼性をどう評価すべきか、その実情を探ります。
大手メディア報道の落とし穴:情報見極めの肝要性
国際情勢に関する報道では、タブロイド紙だけでなく、米国の『ニューズウィーク』、『フォーブス』、『ブルームバーグ』といった大手メディアや、特に『ウォールストリート・ジャーナル』のような経済紙でも誤報が見受けられることがあります。国際紛争においては、未確認情報が掲載されるケースも少なくありません。ニュースを日々追いかける中で、それぞれのメディアが持つ「報道の癖」や「スタンス」を経験則で理解することは、情報の真偽を判断する上で不可欠です。小泉氏も、情報蓄積による「相場観」の形成が重要であると指摘します。
 ロシアのプーチン大統領、国際情勢における情報戦の中心人物として(2025年9月撮影)
ロシアのプーチン大統領、国際情勢における情報戦の中心人物として(2025年9月撮影)
シンクタンク情報も絶対ではない:クロスチェックの重要性
メディアだけでなく、世界最高水準とされるイギリスの研究機関RUSI(王立防衛安全保障研究所)のようなシンクタンクのレポートでも、ウクライナ侵攻初期にロシア側の内部情報に関する誤った記述があったように、非公開の内部情報は確認が難しく、細かいミスはどこでも起こり得ます。日々のニュースの背景を深く理解するためには、世界中の多様なメディアやシンクタンクを参照しつつも、そこで報じられる情報が「絶対ではない」という意識を常に持つ必要があります。そして、最も重要なのは、複数の情報源で裏付けを取る「クロスチェック」の作業であり、情報が更新された際には、ためらわずに自身の認識を更新することです。
記者名から読み解く情報源の強み
情報を評価する上で、記事の署名、すなわち「記者名」も重要な手掛かりとなります。特定の分野で強い情報源を持つ記者がいることは珍しくありません。例えば、アメリカの軍事マニア向けの新興サイト「ウォーゾーン」では、ウクライナ国防省情報総局のブダノウ長官の独占インタビューが掲載されることがあります。これは、元々フロリダ州の地方紙記者で米軍基地担当だったこの記者が、現地の退役軍人会や特殊作戦部隊のOB人脈を通じて、ウクライナ情報総局と強いコネクションを持っていることによるものです。このように、情報発信者の人名と背景に着目することで、情報の「解像度」を高めることが可能になります。
結論
国際情勢、特にロシア・ウクライナ戦争のような複雑な紛争に関する情報は、多岐にわたり、その全てが信頼できるわけではありません。大手メディア、シンクタンク、さらには専門家の情報であっても、常に批判的な視点を持ち、複数の情報源で「クロスチェック」を行うことが不可欠です。また、情報発信者の「個性」や「背景」、そして「記者名」に注目することで、情報の深層を読み解く力が養われます。我々読者には、情報の受け手として能動的に学び、常に更新される情報に対応する「メディアリテラシー」が強く求められています。
参考文献
- PRESIDENT Online (プレジデントオンライン)
- Yahoo!ニュース
- 『国際情勢を読み解く技術』(宝島社) – 小泉悠、黒井文太郎