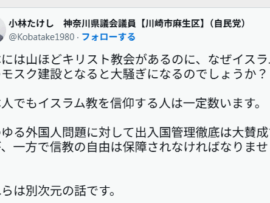中島京子氏の小説・映画『長いお別れ』でも描かれた認知症は、記憶の喪失と共にその人らしさが失われていくような、独特の喪失感を家族にもたらします。一般的には高齢者の病気として認識されがちですが、65歳未満で発症する「若年性認知症」も存在します。この記事では、近畿地方に住む田中花畝さん(仮名)の母親が50代で若年性認知症を発症し、家族が病気と向き合った10年間の道のりをご紹介します。
若年性認知症と診断されるまでの道のり:脳腫瘍手術後の変化
田中さんの母親が50代の頃に患った脳腫瘍が、その後の認知症発症のきっかけでした。手術は成功したものの、母親は近所の知人の家が分からなくなったり、会話が噛み合わないといった異変が周囲から指摘されるようになりました。当時20代で東京で働いていた田中さんは、ちょうど帰郷を考えていたこともあり、母親との同居を決意します。
当初、若い年齢での発症だったため、家族も周囲も「認知症」だとは思いもしませんでした。高次脳機能障害や手術の後遺症ではないかと考えられていたと言います。後に医師からは、脳血管性認知症とアルツハイマー型認知症の混合型である可能性を指摘されました。
「いつか元に戻る」という希望と現実:病気の進行と母親の苦悩
田中さんは、同居生活を始めるうちに母親の認知機能が「いずれ元に戻る」と信じていました。母親は身体的には元気で、見た目も普通の50代の女性だったからです。「食生活を見直したり、脳トレをさせたり、本に書いてあることを全部やってみるような感じでした」と田中さんは当時を振り返ります。
それまでパートタイムで家計を支え、家事をこなし、家庭を切り盛りしてきた母親。若い頃から病気がちだったものの、「もし生まれ変わったら次は健康な体で生まれてくる。そのためにこの体の中にある病気を、今の人生で全部出し切って闘うから」と前向きに自身の体調管理に努めてきた人でした。
しかし、認知症発症後、母親は徐々に計算ができなくなり、数分前に話したことさえ忘れてしまうようになりました。田中さんは、「物忘れが始まって、すごく不安そうにしていました。『認知症になりたくない』とよく泣いていました」と、当時の母親の精神的な苦悩を語ります。病気が進行するにつれ、大好きだった趣味への興味を失い、無表情で気力がない状態になっていきました。
ある時、母親が一人でスーパーに卵を買いに出かけたものの、何も買わずに戻ってきたことがありました。田中さんはこの出来事を鮮明に記憶しており、その際、失意の母親に一瞬とはいえ、あきれた顔を見せてしまったことを今でも深く後悔していると言います。料理などの複雑な家事は、母親一人では難しくなっていきました。
「よく店のレジ袋を小さく折りたたんで、ゴミ袋に再利用したりしますよね。この頃の母は、それを朝から晩まで折っているんです。『そんなに折らなくていいよ』って言っても、ずーっと折り続けてる。父がきれい好きだったので、母なりに意味があったのかなって」。このような、特定の行動を繰り返すといった症状も現れ始めました。
 50代で若年性認知症を発症し、家族が介護に奮闘する母親の姿
50代で若年性認知症を発症し、家族が介護に奮闘する母親の姿
若年性認知症は、患者本人だけでなく、その家族にも大きな影響を与えます。病気への理解と、変化していく状況への適応は、家族にとって長い闘いとなります。田中さんのように、母親の病と向き合い、支え続ける家族の姿は、多くの人々に共感と示唆を与えます。早期発見と適切な支援の重要性が、改めて浮き彫りになる事例と言えるでしょう。