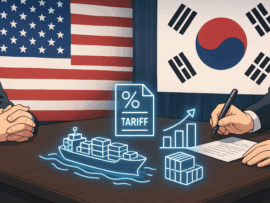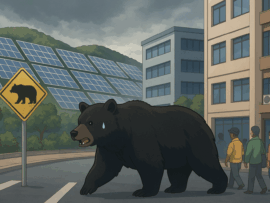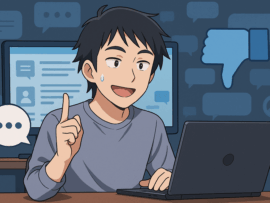高校野球の日本一を決める「夏の甲子園大会」は、近年深刻化する猛暑との戦いが大きな焦点となっています。特に今年は、選手や観客を熱中症から守るため、気温が上昇する日中の時間帯を避け、午前と夕方に分けて試合を行う「朝夕2部制」が、昨年の3日間から5日間(当初は6日間の予定が天候による順延で1日短縮)へと拡大して導入されました。この新たな試みは一定の成果を見せた一方で、大会運営における新たな課題も浮上しています。
 灼熱の甲子園でプレーする高校球児たち
灼熱の甲子園でプレーする高校球児たち
「朝夕2部制」導入の成果と評価
今大会で「朝夕2部制」が実施された開幕から5日間において、熱中症の疑いで救護室を受診した選手の件数は15試合で8件と、昨年の同時期と比較して12件の大幅な減少を見せました。また、観客の救護室受診も49件(うち熱中症の疑いは19件)で、昨年の130件(同71件)から大きく減少しました。野球専門サイト「Full-Count」は、グラウンド上で足をつる選手が続出した第2日においても、観客の救護室受診が11人、熱中症疑いが8人にとどまったことを報じ、救護室の医師からは「きょうは2部制の効果だった」との声が上がったと伝えています。このことから、朝夕2部制が熱中症対策として一定の有効性を示したと言えるでしょう。しかし、第1日から第5日までの平均気温が30.3度と、昨年より2度低かったという気象条件も、その効果に寄与した可能性があります。
多角的な猛暑対策と新たな課題
甲子園大会を巡っては、近年多岐にわたる猛暑対策が導入されてきました。日本高校野球連盟(高野連)と朝日新聞は、今年の開幕日の朝刊1面で「大会本部は安全対策や暑さ対策に万全を期します」と表明。2023年からは5回終了時の水分補給と身体冷却を目的とした「クーリングタイム」が導入され、今年はさらに試合前のノック時間の短縮や、その実施の有無を選択できる柔軟な対応が取られました。すでに球児たちが着用している熱を反射する白色シューズの導入も審判にまで広がるなど、対策は着実に進んでいます。
「2部制」が抱える意外な弱点
しかし、夏場の集中開催という根本的な枠組みを維持する以上、猛烈な暑さに直面するという課題は避けられません。主催者側が限られた日程の中で様々な工夫を凝らす中、今大会の「朝夕2部制」は新たな弱点も露呈しました。試合終了時間が遅くなることで選手の生活リズムに影響を与える可能性や、悪天候による一時中断の判断が難しくなるという課題です。特に、天候による順延が発生した場合、過密日程がさらに厳しくなる懸念も指摘されています。
今後の「夏の甲子園」を見据えて
“小手先”の猛暑対策で過密日程を消化し続ける「夏の甲子園」が、果たして現代の気候変動に即しているのか、という根本的な問いが突きつけられています。猛暑が年々厳しさを増す中、5年後、10年後の夏を見据えたとき、大会のあり方そのものについて抜本的な見直しを念頭に置いた、より踏み込んだ議論を深める時期が差し迫っていると言えるでしょう。選手たちの健康と安全、そして大会の持続可能性を確保するためには、これまでの慣例にとらわれない大胆な発想と具体的な行動が求められています。