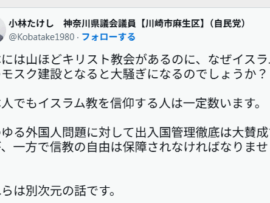日本が国家の破滅へと突き進んだ昭和期において、その中心にあった陸軍組織の機能不全は、長らく多くの議論を呼んできました。彼らはいかにして、なぜ国家を破滅の淵に追いやったのか?この深遠な問いに対し、昭和史研究家やノンフィクション作家、軍事専門家といった最高の知見を持つメンバーが集い、特別大座談会「昭和の陸軍 日本型組織の失敗」が開催されました。本稿では、その一部を抜粋し、特に陸軍が抱えていた「制度的欠陥」に焦点を当て、その歴史的背景と現代にも通じる組織論的課題を深く掘り下げていきます。
 東條英機の肖像画。昭和期の日本の軍人、政治家として知られる。
東條英機の肖像画。昭和期の日本の軍人、政治家として知られる。
参謀本部制度に見られる構造的欠陥
元陸将補の黒野耐氏は、陸軍の組織が、一部の参謀による暴走を許す「制度的欠陥」を内包していたと指摘します。この問題の根源は、明治11年(1878年)に山縣有朋が参謀本部を組織した際に遡ります。山縣は、軍内で政治的に対立していた三浦梧楼や谷干城といった有力将軍たちの力を削ぎ、参謀本部長である自身の権力を確立するため、近衛や鎮台(後の師団)司令部の参謀を参謀本部が直接指揮できるという独自の制度を創設しました。
この制度は、参謀本部が配下の参謀を通じて、「これが天皇の考えだ」と称して作戦を立案すれば、司令官はその案を破棄できないという構造を生み出しました。統帥権を盾に天皇を持ち出されると、いかなる反対意見も封殺されかねません。この流れが行き着いた先が、司令官を差し置いて参謀が軍を差配する「幕僚統帥」という異常な状態だったのです。これは、命令系統が逆転し、専門家である参謀が本来の指揮官の役割を侵食する事態を招きました。
改革の試みとその挫折
このような制度的欠陥を認識し、改革を試みた人物は他にもいました。福田和也氏が触れたように、三浦梧楼は原敬内閣の際に参謀本部を解体しようと画策したこともあります。しかし、これらの改革は結局、失敗に終わります。その背景には、参謀本部が発足した際に制定された「参謀総長は全陸軍の参謀を統轄する」という「参謀本部条例」が強力に存続し続けたことがあります。
黒野氏は、自身が防衛大学校をはじめとする教育機関で欧米流の組織論を学んだ経験から、この条例を最初に読んだ時に強い違和感を覚えたと語ります。欧米の常識では、参謀は上官である指揮官の補佐役、いわば「小間使い」であるべき存在です。それにもかかわらず、上官を差し置いて参謀本部の命令を実行するというのは、考えられないことでした。この独自の制度が、山縣有朋の権力闘争の過程で作り上げられた日本陸軍特有の仕組みであると理解できたのは、その制度の歴史を深く学んで初めてのことだったといいます。この組織論的な歪みが、後の陸軍の暴走の一因となります。
プロシア軍との比較に見る解釈の拡大
防衛大学校教授の戸部良一氏は、この制度の背景には山縣個人の思惑だけでなく、日本がモデルとしたプロシア軍の参謀組織の影響もあった可能性を指摘します。ドイツのプロシア軍においても、各地の独立した部隊を中央部が統轄するために参謀を派遣し、彼らが連絡調整を行う役割を担っていました。
戸部氏の見解は、プロシア軍の制度が日本において「拡大解釈」され、本来の連絡調整役であった参謀が、あたかも部隊全体を統括する権限を持つかのように振る舞う「幕僚統帥」へと発展してしまった可能性を示唆しています。これは、先進的な組織形態を取り入れつつも、その本質的な理解や運用において独自の解釈が加わることで、予期せぬ機能不全を引き起こすという、組織論における普遍的な課題を浮き彫りにしています。
結論
昭和陸軍が国家を破滅へと導いた背景には、複雑な要因が絡み合っていますが、今回の座談会で浮き彫りになった「参謀本部制度の構造的欠陥」は、その核心の一つであると言えるでしょう。山縣有朋による権力掌握のための制度設計、それが生み出した「幕僚統帥」という歪んだ指揮系統、そして海外の組織論の安易な「拡大解釈」。これらが複合的に作用し、陸軍が本来の役割を超えて暴走する土壌を形成しました。
この歴史的教訓は、現代の組織運営においても示唆に富んでいます。いかに優れた制度であっても、その運用が歪んだり、個人の権力欲が介入したりすることで、組織全体が機能不全に陥るリスクをはらんでいることを、昭和陸軍の事例は私たちに強く訴えかけています。過去の失敗から学び、健全な組織体制を築くことの重要性を改めて認識する必要があるでしょう。
参考文献
- 初出: 平成19年(2007年)「文藝春秋」6月号
- Yahoo!ニュース: https://news.yahoo.co.jp/articles/a94526e8468b61508c81619ff36f08460afd8346